夏になるとホラーが増える。
 焦げ団子
焦げ団子でも血が出たり叫び声が飛び交うやつはもうお腹いっぱい。
そんな団子にちょうどいいのが、夏目漱石『夢十夜』の第三夜。
古典のくせに、これが意外と怖いんだな。
派手な演出ゼロ、音も光もない。なのに、ぞわっとくる。
いわゆる稲川淳二系のクラシカルな怪談なのだが、なかなか完成度が高い。今回は、そんな夢十夜の第三夜、解説していく。
第一夜からみたい方はこちら!


※ 夢十夜まとめ一覧→[夢十夜はじめました|夏目漱石レビューの入口はこちら]
他の作家さん一覧はこちらからどうぞ。→[焦げ団子の推し作家・人物一覧]
「何があるのかざっくり見たい」という方は、先にこっちから眺めてもOK。
あらすじ|恐怖の一夜


「こんな夢を見た」で始まるこの第三夜。
語り手は六歳の盲目の子供を背負って、暗い田舎道を歩いている。声は子供、でも口調は妙に大人びている。
「お父さん、重いかい?」
「今に重くなるよ」
背中の子は、まるで語り手の過去・現在・未来を全部知っているかのように喋る。そして突然、こう言い出す。
「御前がおれを殺したのは、今から百年前だね」



――ぞわっ。
背負ってるのは自分がかつて殺した盲目の子供。
自分が人間だった頃の罪が、夢の中でよみがえってくる。
その瞬間、背中の子供が石地蔵のようにずっしり重くなる。
なぜ人は“怖い夢”を見るのか?
団子はよく「追いかけられる夢」を見る。相手は見えない、理由もわからない。でも全力で逃げてる。
――で、目が覚めたらドッと疲れてる。
…あれって一体なんなんだ?
実は、「怖い夢=意味がある」という説は意外と多い。
脳科学や心理学では、こんなふうに解釈されてる。
夢は「感情の処理装置」説
夢は、起きてる間に感じた強い感情
――とくに恐怖・不安・罪悪感を脳が整理するプロセスだと言われてる。
つまり、現実で感じきれなかった感情を、夢の中で再体験して処理しようとしている。
■「脳のシミュレーション機能」説
もうひとつの説は、夢は危機的状況の練習。
「逃げる」「追われる」などのシーンを脳内で繰り返しておくことで、
もし現実で似た場面が起きたときにすぐ反応できるよう、本能的な訓練をしているという話も。
■「PTSDの夢」に似てるケースも
強いトラウマを持つ人が、似た状況を何度も夢で見てしまうことがある。
これは単なる記憶じゃなく、脳が“未解決の感情”として処理し続けているから。
つまり、夢に出てくる怖さは、現実で消化しきれていない“何か”の影かもしれない。
漱石って怪談書くタイプだったの?
漱石=『坊っちゃん』のユーモアおじさん、ってイメージあるかもだけど、実はこういう不気味な話もかなり得意。
彼、学生時代から怪談や志怪小説に触れていて、仏教の輪廻思想や罪の意識なんかにも興味があった。
第三夜は、明治の近代人として合理主義を掲げつつ、その裏でこっそり「罪とか命の終わりとか、やっぱ怖いんだよな…」とつぶやくような、そんな作品。



地味に、夏目漱石の二面性が出てるんだよな。
第ニ夜はこちら!
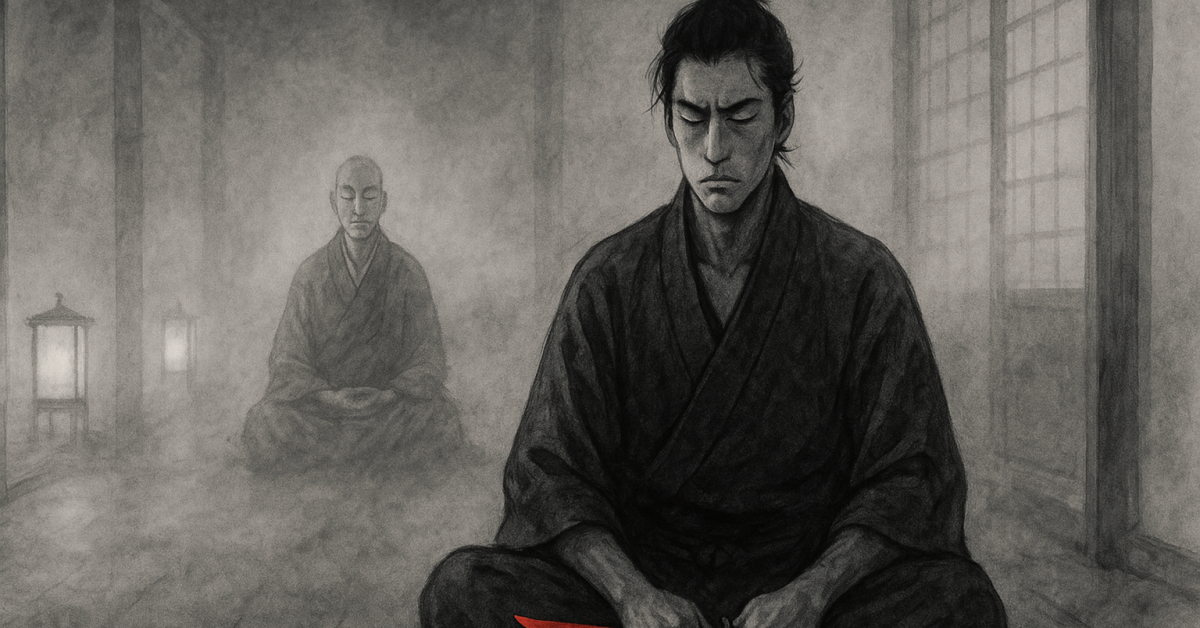
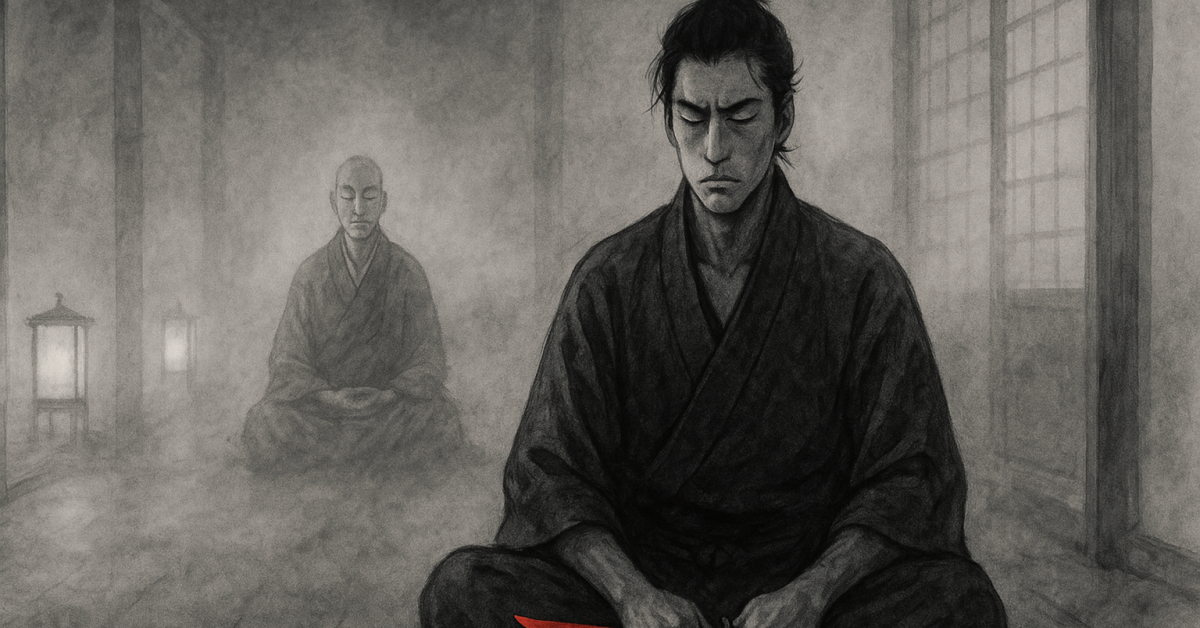
ここまで読んでくれた方へ。
もっといろんな話を見てみたい方は、全記事まとめページもどうぞ。
→夢十夜まとめ一覧→[夢十夜はじめました|夏目漱石レビューの入口はこちら]
→他の作家さん一覧はこちらからどうぞ。→[焦げ団子の推し作家・人物一覧]
何気ない記事から刺さるものが見つかるかもしれません。
