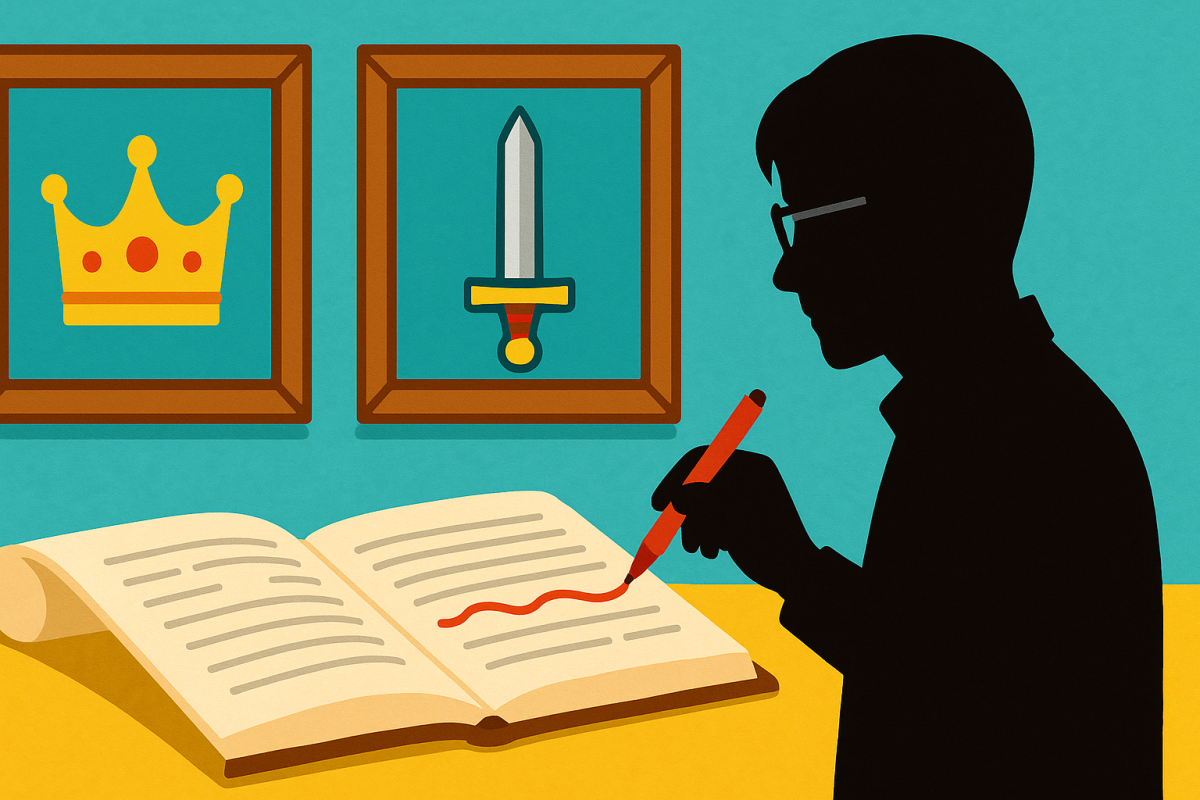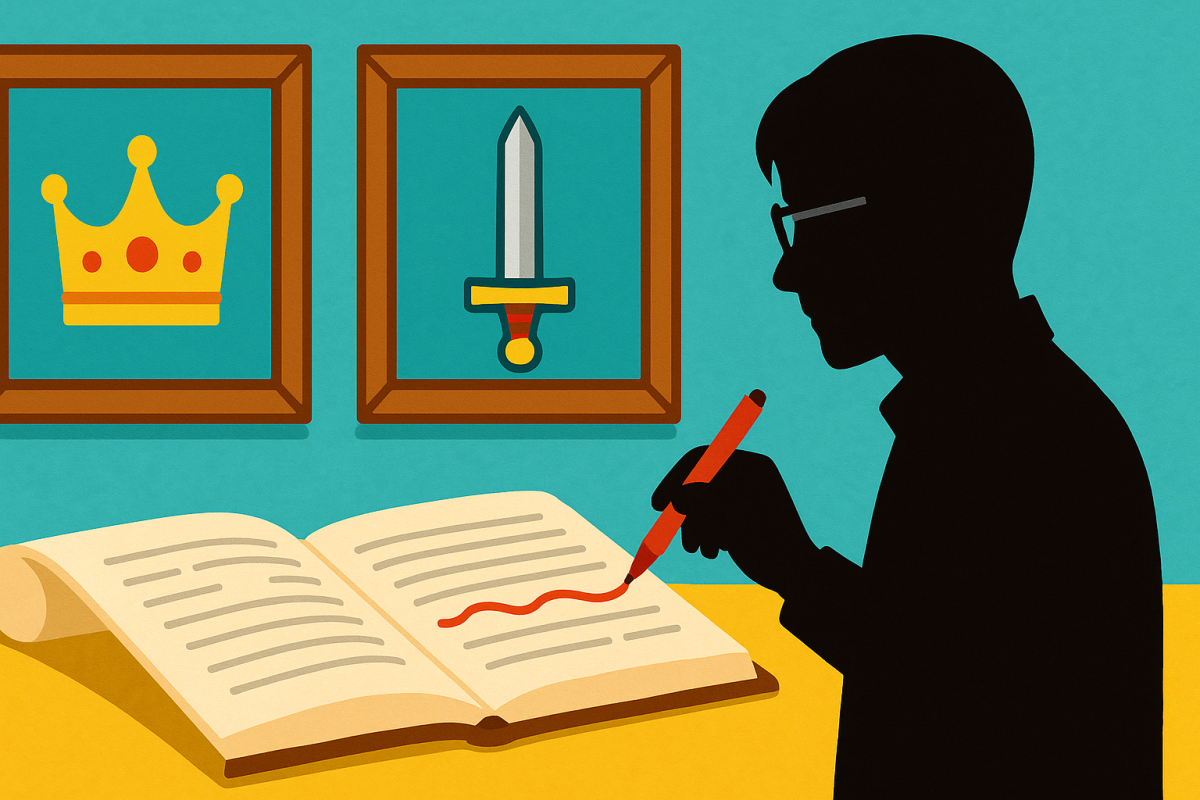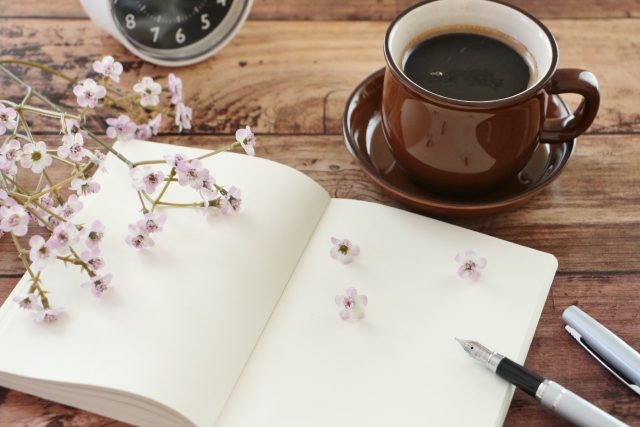焦げ団子
焦げ団子昔の偉人って、
どうしてあんなに日記を書いてたんだろうな。
清少納言、兼好法師、芭蕉、ルソー…
読む側からすれば「おお、名文…!」だけど、当の本人たちは、たぶんただの日常の記録だったはず。
団子的にはまったく真似できない。
というのも、団子──日記が1ヶ月以上続いた試しがない。
やる気だけはあったんだよ。
高い日記帳も買った。インクがいい感じのペンも用意した。
でも、だいたい数ページで放置。
読み返すと恥ずかしすぎて全部燃やしたくなる。
なんでこんなテンションだったん?って未来の自分が冷めた目してくるの、ほんとやめて。
だからこそ思うわけ。
なんであの人たちは、こんなにも静かに、自分を言葉にして残し続けられたんだろうって。
気まぐれでもない。
義務でもない。
でも、彼らの中には「書かずにはいられなかった何か」が、たしかにあった。
というわけで今回は、
団子的に「昔の人がどうしてあんなに真剣に書いてたのか」
その理由を、軽く皮肉りながら探っていくぞ🍡



そして次こそ三日坊主にならない日記を書く!
【関連記事】昔の人も今の人と同じようなことで悩んでいた?


書くことは、昔の人にとって“思考の補助輪”だった
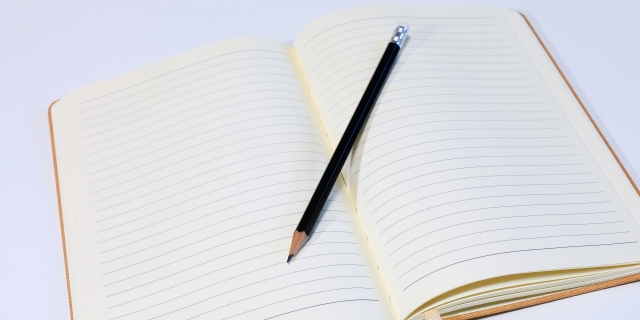
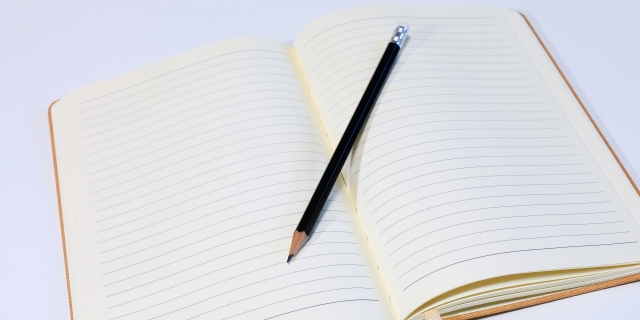
何かについて深く考えたいとき、頭の中だけでぐるぐるしても整理できないことってあるよな。
考えれば考えるほど、迷子になるやつ。
団子的には、まさにこれが「書くことでしか整わない」ってやつだと思ってる。
たとえば、徒然草を書いた兼好法師。
彼が綴ったのはただの感想とかぼやきじゃない。
「世の中ってこうだよな」っていう、どうにもならないもやもやを言葉にすることで、やっと自分の中で落とし所を見つけてる。
あの人の随筆、読み返すとだいたい「生きづらさの言語化」なんだよ。
しかも、めっちゃ冴えてる。
清少納言もそうだ。
枕草子って、「季節の美しさを称えた名文集」みたいに扱われがちだけど、実際はツッコミと推し語りの応酬みたいな内容ばっか。
「こういう男は嫌」「この女はイケてない」「〇〇様は尊い」
完全に今で言うnote。
つまりこのふたりって、「思考を外に出さないと自分でも見えない」タイプだったと思う。
頭の中でまとまってる風に見えて、たぶん実際はそうじゃない。
書いてる途中で、あっ、そういうことかってなってたはず。
団子もこれ、めちゃくちゃ共感する。
何かについて「言語化して初めて腑に落ちる」ことって多くて、誰かと会話してる最中に答えが出てくることもあるし、さっきまで書けなかった原稿が、雑にメモった瞬間にスイッチ入ることもある。



頭で完結できる人はさ、本なんか書かないんだよ。



書かないと生きづらいから、みんな黙ってペン持ってた。
脳内って、意外と信用できない。
昔の偉人たちが「書きながら考える」タイプだったって考えると、日記や随筆が感情のゴミ捨て場じゃなくて、思考の試運転場だったのも納得がいく。
書くことでしか感情を捌けなかった時代
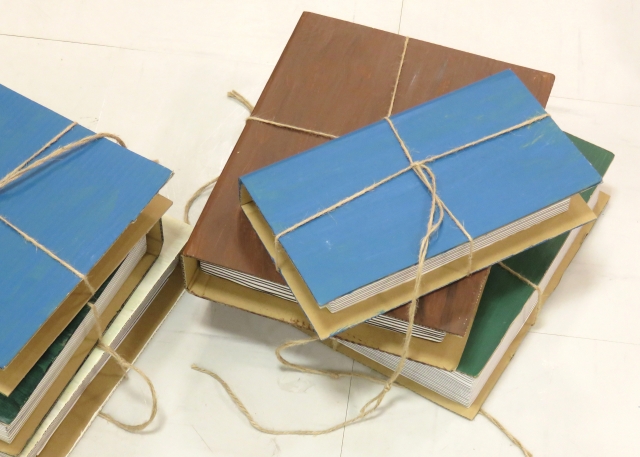
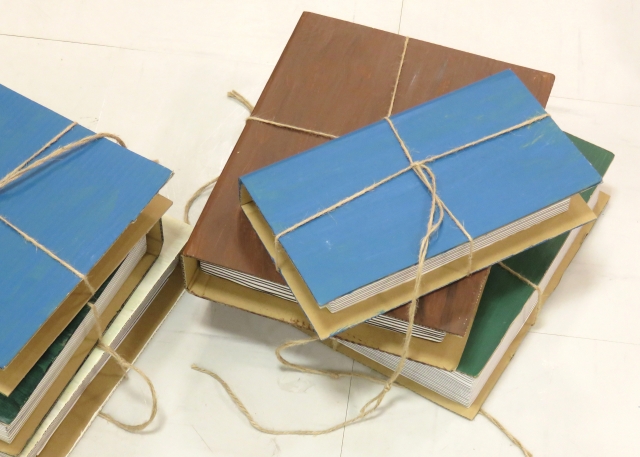
昔の人って、基本的に誰にも話せない状態で生きてた。
今みたいに友達にLINEで愚痴ったり、推しにスパチャ投げたり、AIに「疲れた」って言うことすらできない。
それでも人間だから、イラッともするし、寂しくもなる。
じゃあどうしてたかっていうと、たぶん…書いてたんだよな。
清少納言の枕草子、ちゃんと読んだことある人はわかると思うけど、あれ、半分くらい“嫌味と陰口”でできてる。
「この女は無理」「あの人のセンスが解せぬ」みたいなブツブツがめっちゃ多い。
あと、好きな人に対する情熱もエグい。
今で言う非公開note課金記事みたいなやつ。あれ、めちゃくちゃ情緒が生々しい。
兼好法師もそう。
徒然草って、「世の中はどうせうまくいかないし、全部無常」っていう人生ハードモード系の達観ぼやき日記で、ところどころ人間への失望がにじんでる。
書いてないと自我が保てなかったんじゃないかってくらい、独り言の密度が高い。
団子は昔、ブログで誰にも見せない愚痴日記を書いてた時期があるけど、あれに近い。
誰かに伝えるんじゃなくて、「とにかく言いたい。捨てたい」だけの文章。
文字にしないとやってられなかったんだと思う。
書いてるうちに冷静になれるし、こんなことで怒ってたのか…って自分を見下ろせる瞬間もくる。
それが救いになってた。
今でこそ日記=前向きな習慣ってイメージあるけど、昔の人にとってはむしろ「生きるの、しんどいから書いてた」みたいなとこ、絶対ある。



あの頃の筆者たち、全員SNSあったら絶対炎上してたと思う。



でも、そのくらいの心の毒がある文章のほうが
読みごたえあるのも事実。
「書くこと」は、生きてた証を刻むことだった
現代なら、誰でも日記を書ける。
スマホに打ち込むのもよし、紙に書くのもよし。
書きたくなければ書かないで生きていける。
でも昔は──そもそも書ける人間が限られてた。
文字を学ぶ環境があるのは、貴族か僧侶か、一部の知識層。
だからこそ、「書く」ってこと自体に階層的な意味があった。
清少納言や兼好法師、芭蕉みたいに書き残せる人たちは、そもそも「記録を持てる人間」だったんだ。
そしてそれは、裏を返せば──自分の存在を残せる特権でもあった。
団子が思うに、あの人たちは、「言葉にして残すことで、自分を確かに存在させてた」。
たとえば芭蕉。
旅に出て、いちいち風景や感情を記録してたけど、あれってたぶん、どこかで「この瞬間を誰かに残したい」って気持ちがあったと思う。
それが評価されるかは関係なくて、「自分がここにいた」っていう、ささやかな刻印。
現代人のSNSと何が違うかっていうと、あっちはバズりもしないのに書いてるとこ。
誰に届くかもわからないまま、自分の記録だけをひたすら残す。
それってたぶん、「いつか寿命を迎えるのは仕方ないけど、完全に消えるのは嫌だった」って気持ちなんじゃないかと思う。
書くことは、ただの発信じゃなかった。
記録=生きた証だった。



人は消える。でも言葉は残る。



だったら自分の中の「どうでもいいこと」すら、
文字にして刻みたくなるときもあるだろ。
まとめ:書くことで、人は「考え」、癒え、残ろうとした
書くことで、人は「考え」、
書くことで、人は「癒え」、
書くことで、人は「残ろうとした」。
昔の人が日記を書いていた理由は、たぶん「記録を残したいから」じゃない。
まず最初にあったのは、書かないとやってられなかったっていう生身の感情だったと思う。
頭の中を整理するために、言えないことを吐き出すために、そして、自分という存在をこの世界に引っかけるためにだ。
団子みたいに三日坊主の人間には想像つかないけど、彼らにとって書くことは、生き方そのものだったんじゃないかと思う。



思えば団子がこうしてブログを書いてるのも、
「誰かに届くかも」って気持ちが
どっかにあるからかもしれん。
SNSやブログやnoteで、「どうでもいいこと書いちゃった」と思う日があるかもしれない。
でも、それが誰かに刺さるかもしれない。
…って思うと、ちょっとだけ、今日もなにか書きたくなってくるよな。
【関連記事】昔の人も今の人と同じようなことで悩んでいた?シリーズ