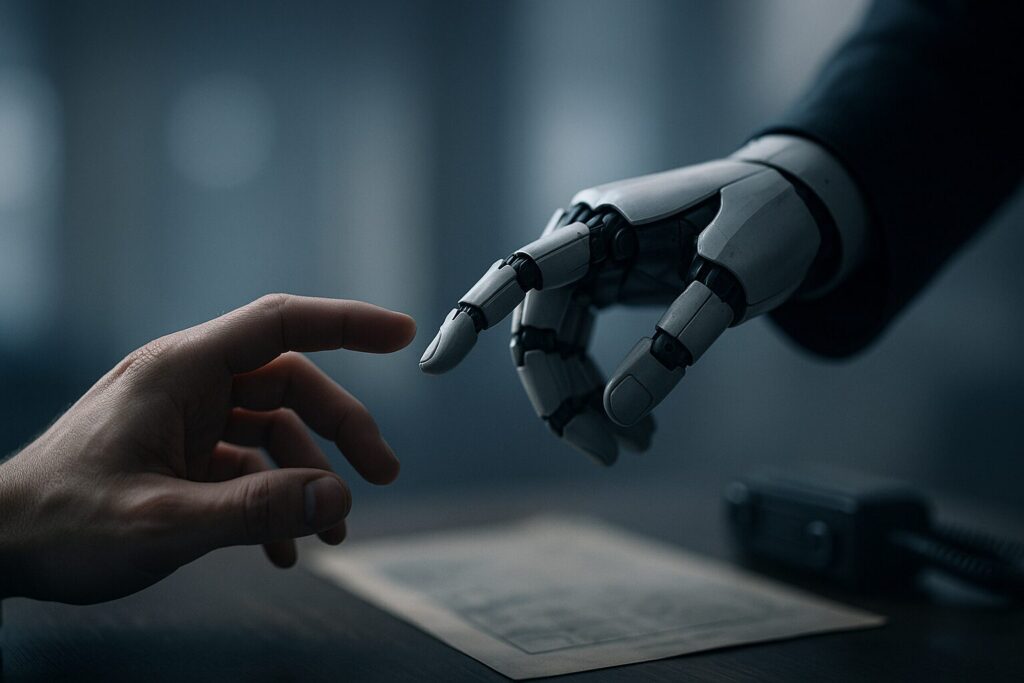みなさん、プリングルス(=正式名称:プリングルズ)というお菓子をご存じだろうか?
そう、あの筒に入ったパリパリのポテトスナックのことだ。
だがしかし、イギリスでは一時期「これはポテトチップスではない、ケーキである」という主張が本気で飛び交っていた時代があった。
しかもこれ、冗談でもなんでもなく、裁判沙汰になっていた。
企業側の主張はこうだ:
 P&G
P&Gプリングルスはじゃがいもじゃなくて粉から作ってるし、形も特殊。
これはもはやポテトチップスではなく、むしろ……ケーキです。



は?
イギリス政府を相手に、P&G(当時プリングルスを販売していた企業)が本気で税制の抜け道を狙ったスナックの定義論争、その中身を団子的におもしろおかしくまとめてみたぞ!


「スナック菓子=課税対象」の理由とは?イギリスの軽減税率と食品分類の仕組み
実はイギリスって、食べ物にかかる税金にめちゃくちゃシビアな国だった。
「健康な食品にはかけないけど、ジャンクフードにはしっかり税金とるよ」というスタンスで、「付加価値税(VAT)」という制度を導入していた。
で、このVAT制度の基本ルールがこちら:
- パンや野菜などの基本的な食料品 → 非課税(0%)
- チョコ、スナック、炭酸飲料などの贅沢&ジャンク扱い → 標準税率(当時17.5%)
つまり、体に良さそうなものは税金かけないけど、「おやつ」や「お菓子」認定されたら課税対象になるってわけ。
で、ここで問題になったのが……
プリングルス「うちはポテチじゃない。ケーキです(真顔)」
そう、みんな大好き筒入りポテチことプリングルス。
イギリスでは当時、「ポテトチップス=スナック類」として、しっかり課税対象になっていた。
でもP&G(当時の販売元)はこう主張したんだ。



うちのプリングルスはじゃがいもスライスして揚げてるんじゃなくて、一度粉状にしてから成形して焼いてます。
ポテチっぽいけど、厳密には成型スナック。



……てかこれ、焼き菓子とかケーキみたいなもんじゃない?



いやいやいやいやいや
この税金逃れ大作戦の行方は……次章へ!
プリングルスはなぜケーキだと主張したのか?企業が使った税回避ロジックを解説


さて、「スナック菓子には税金かけるけど、基本的な食品にはかけない」——
そんなイギリスの軽減税率制度(付加価値税=VAT)に、まさかの挑戦状を叩きつけたのがプリングルスだ。
P&G(当時の販売元)が裁判で本気で主張したのがこちら:
「プリングルスはスナックじゃない。あれは……ケーキです。」



ちょっと何言ってるか分からない。
でもこれは冗談ではなく、スナック扱い=標準税率(17.5%)課税を避けるための、マジの法廷戦術だった。
企業側の理屈はこう:
- プリングルスって原材料のじゃがいもが42%しか入ってないんですよ。
- 小麦粉やとうもろこし粉を混ぜて生地を作ってるんですよ。
- スライスして揚げてるわけじゃないんで、ポテトチップスじゃないんです。
そしてこう畳みかける。



うちの製法は焼く。こねて焼いてる。
つまりこれは……スポンジケーキと同じ“焼き菓子”です!
──いやもう無理がありすぎる。
でもこの屁理屈、もし通れば17.5%の税金がゼロになる。
だから本気。死活問題。どこまでもケーキになりたがるプリングルス。
結果的には国側が「いやいや、見た目も食べ方もスナックやろがい」として、プリングルス=課税対象と判断したが、この一件は今でも「食品ジャンルの定義って、どこまでがアリなのか?」というマーケティング・税制の境界線をめぐる歴史的なネタ裁判として語り継がれている。



税金のかかり方で売上が大きく左右されるなら、必死にもなるか。
イギリス政府の反論「プリングルスはポテチだろ?」法廷での争点はここだった!


さて、「プリングルスはケーキである」と本気で主張してきた企業側に対し、イギリス政府(正確には税務当局)はどう反論したのか?
答えはシンプル、そしてツッコミ満載だった。
「どう見てもスナックやん」理論
イギリスの税務当局は、こんな感じで反論している:
- プリングルスはしょっぱい味で、サクサク食感で、袋菓子感覚で食べられている。
- しかも販売方法が筒入りでスナック菓子コーナーに置かれている。
- 消費者はどう見ても「ポテトスナック」として認識してるし、“ポテトチップスみたいなやつ”として買ってる。
つまり、「お前の主張するケーキ要素、誰も感じてねえよ!」という論破である。
たとえ製法がちょっと違うとしても、見た目・食感・味・売られ方すべてが“スナック菓子”である以上、「非課税の食品」とは言えない。
成分比率の話も却下
P&G側は「じゃがいも成分が42%しか入ってないからポテチじゃない!」という屁理屈も展開したが、これもあっさり撃沈。
イギリス税務当局いわく:



じゃがいもが4割超えてる時点で、十分“ポテトスナック”認定である。
……まあ、そりゃそうだ。
成分が100%じゃなきゃポテトじゃない論理が通ったら、世の中のハンバーグもカニクリームコロッケも全部“別の何か”になってしまう。
最終的には2009年、イギリス高等法院が「プリングルスはスナックである」と判断し、標準税率17.5%のVAT(付加価値税)課税対象に指定。
P&Gの「ケーキ化」戦略は、ここにあえなく敗北した。



残念だが当然の結果。
裁判には負けてもブランドは勝った?プリングルスの炎上マーケ戦略を考察
裁判には負けた。
最終的に「プリングルスはスナックだから、課税対象ね」とバッサリ。
イギリスではちゃんと VAT(付加価値税)17.5% がかかることになった。
でも。
この裁判、ブランド戦略的にはむしろ“勝利”だった可能性が高い。
というのも、そもそもこの裁判が行われたのは2008〜2009年ごろ。
当時プリングルスって「ちょっと高くて謎なスナック」ってイメージがまだ強かった。
そんな中で、「プリングルスはケーキかもしれない」っていうとんでも理論が話題になり、
しかも国家相手に本気で争う姿勢を見せたことで——
- プリングルスの知名度が爆上がり
- 「やっぱ変わってる会社だよな」ってブランド個性が定着
- 値段が高くてもプレミア感として逆に受け入れられるように
……という、わりと理想的な副産物を手に入れた。
つまりこれは、マーケティング的には「裁判=巨大プロモーション」だった説。
企業としては当然「非課税になればラッキー」と思ってたはずだけど、負けてもちゃんと世間の記憶におもしろ企業として残った。
しかも今なお、「プリングルス ケーキ」で検索されるレベルで語り草になってる。
この税金ごね裁判、ただの脱税トリックじゃなかった。



むしろ屁理屈で国にケンカ売って知名度上げた奇跡の一手だったと思うぞ。
まとめ|「プリングルス=ケーキ」裁判の真の意味とは?ブランドと税制のはざまで起きた珍事
プリングルスが「自分たちはケーキです」と言い張ったのは、単なる節税トリック——と思いきや、そこにはマーケティング的な副産物もあった。
実際、裁判では敗訴して課税対象になったものの、その過程でプリングルスは「常識にケンカを売るスナック」という独自のキャラを確立。
負けても注目を集めた者が、結局は勝者ということを、妙に真面目な裁判沙汰から教えてくれた気がする。
今となっては笑い話だけど、世界中に語り継がれてるという意味で、プリングルスは、税金よりも話題性という大きなリターンを手に入れたのかもしれない。



次にプリングルスを食べるときは「そういえばこれ、ケーキって主張してたんだよな…ww」ってちょっとでも脳裏をよぎってくれたら
それはプリングルスの勝利なのよ
その他海外の珍事件ネタはこちら!
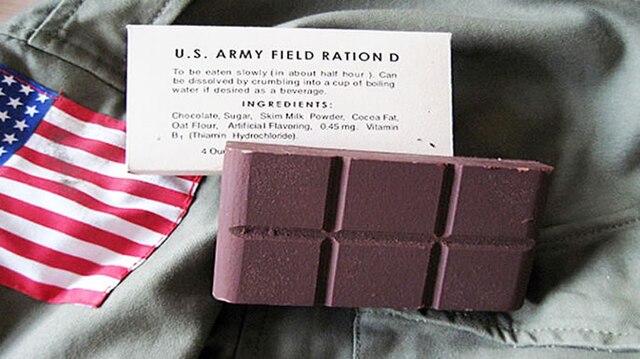
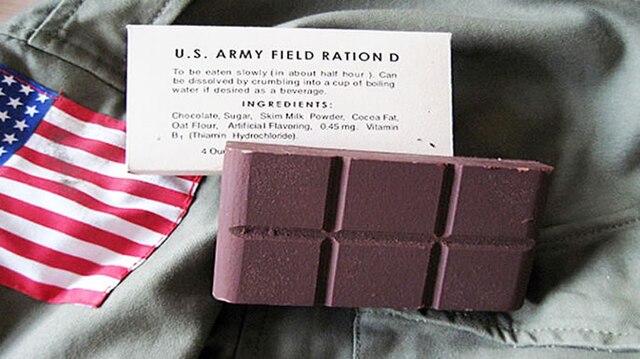


海外カテゴリの最新記事