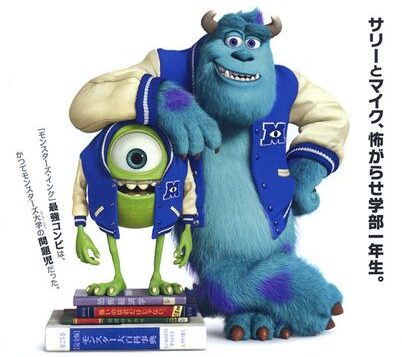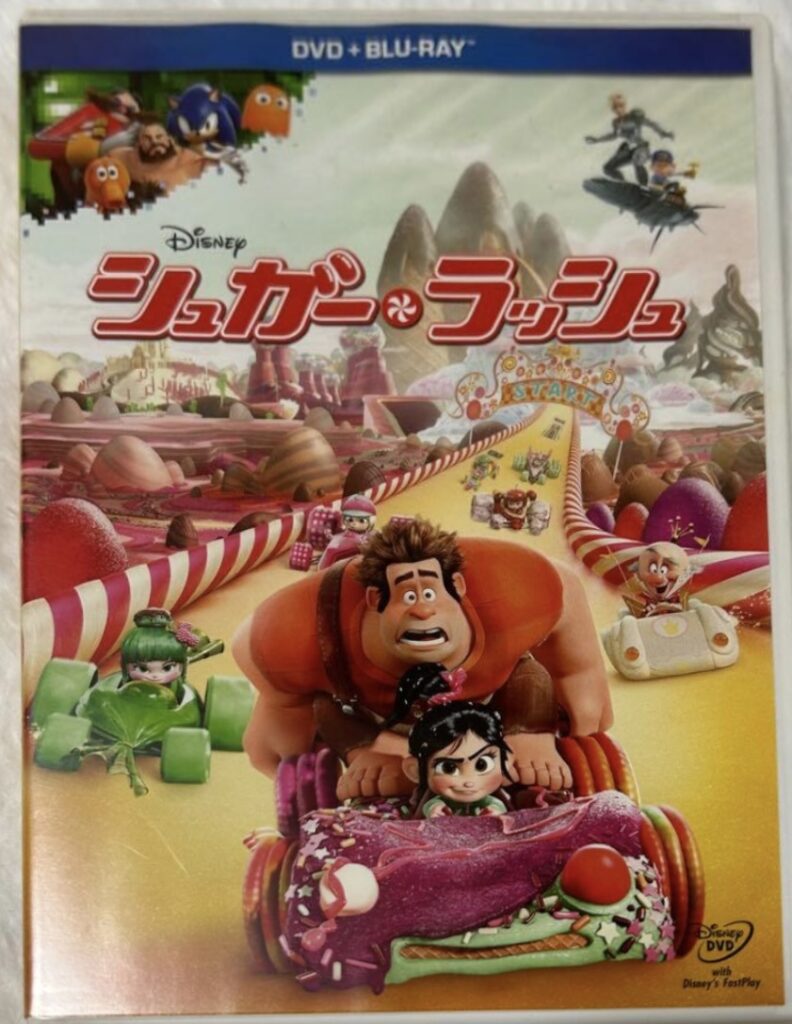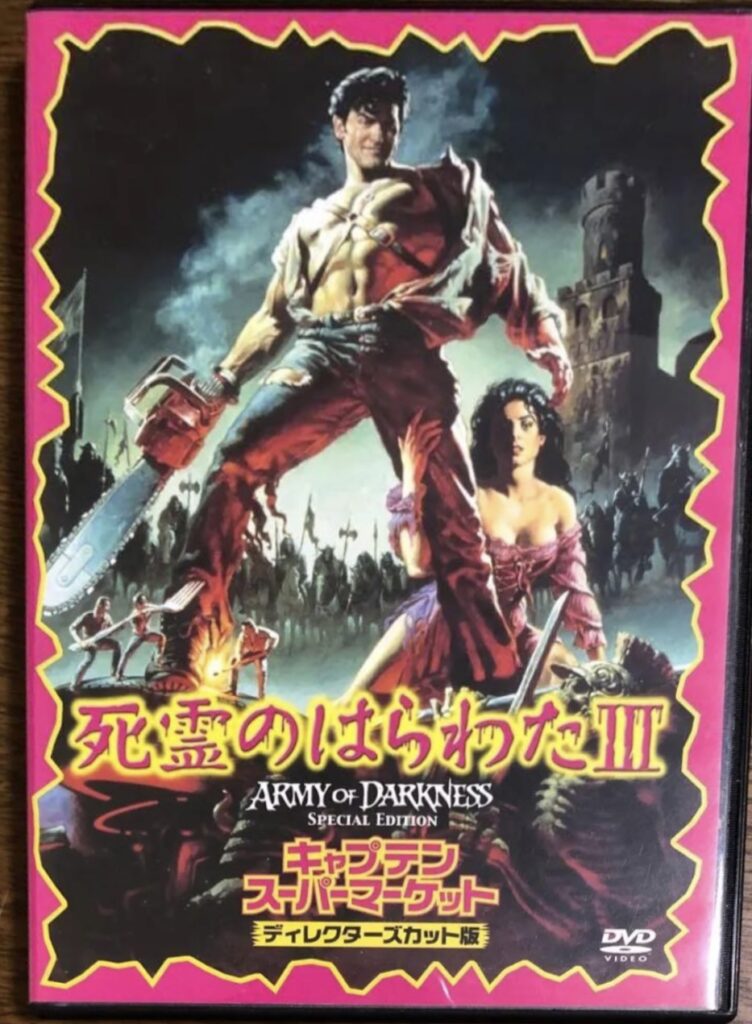みなさんはディズニー映画『ピノキオ』をちゃんと観たことがあるだろうか?
団子は子どもの頃に断片的に見た記憶があるが、子どもがロバにされるシーンが怖すぎて、まともに観る気になれなかった。
でも今回、改めて最初から最後まで観てみた。
…結果、ひとこと。
 焦げ団子
焦げ団子これ、教育とか道徳の話に見せかけた懲罰系ホラーじゃねえか。
人形に命が宿り、「立派な人間になるための旅」が始まる──という表向きのあらすじ。
でもその旅はあまりにも理不尽で、ピノキオは「自分で考えることができない」というだけで、甘い誘惑に流され、だまされ、閉じ込められ、まるでモノのように扱われそうになる。
つまりこれは、
流された人間はとんでもない目に遭う
だからこそ、自分で選べる人間にならなければ、“本当の意味での人間”にはなれない。
そんなディズニー式の怖いくらいリアルな教訓が詰まってる。
ピノキオのあの笑顔の裏にあるのは、従順・教訓・社会のルールを身につけることが人間になる条件として描かれている。


ディズニー映画『ピノキオ』(Pinocchio)ネタバレあらすじ|人形ピノキオ、自由すぎる1日目で地獄を見る
ゼペットじいさんは、木でできた人形「ピノキオ」に命が宿るよう願いをかける。
その願いを受け取ったブルー・フェアリー(青い妖精)がやってきて、なんと本当にピノキオが動き出す。
ただし条件付き。



正直で、勇敢で、思いやりがある子になれば、ほんとうの人間になれる
ということで、喋る良心役・ジミニー・クリケット(コオロギ)をお供に、ピノキオの人間になるための旅が始まる。
しかしここからが地獄。
ピノキオは学校に行くどころか、街でキツネにそそのかされ、サーカス団に売られる。
● 檻に閉じ込められ
● フェアリーに助けられて脱出
● またしても詐欺師に遭遇し、今度は「プレジャーアイランド」へ(誘惑の島)
この島では、子どもたちが酒・タバコ・ビリヤードとやりたい放題。
が、そこにいた子どもたちはロバに変えられ、どこかへ売られていた。
ギリギリで島を脱出したピノキオは、家に戻るもゼペットじいさんが行方不明。
なんと、じいさんはピノキオを探して海に出て、クジラに飲まれていた。
そこでピノキオも海へ。
クジラの中で再会し、火を起こしてクシャミで脱出する。
でも、海で溺れてしまうピノキオ。
奇跡的に命を取り戻し、フェアリーによって本物の人間の男の子に。
こうしてピノキオは、条件付きの奇跡をくぐり抜けて「人間」になったのでした。



……いや、これクソガキが1日目で体験するには重すぎん???
ディズニー映画『ピノキオ』(Pinocchio)|見所・感想


流される者はロバになる──プレジャー・アイランドの地獄絵図
まず外せないのがここ。
ピノキオが連れていかれた「プレジャー・アイランド」は、酒・タバコ・破壊行為やり放題の地上の楽園(に見える地獄)。
で、調子に乗ってた子どもたちはどうなるかって?
→ ロバになります。人間の意識を残したまま。
「ママァァァァ!!」って泣き叫びながら蹄バタバタしてる少年の姿、完全にトラウマ製造機。
これはもう、「自由に生きたいなら、自分の行動には責任持てよ」っていう見せしめ。
しかも、ロバになったらそのまま売られるっていう、ディズニー史上最も生々しい児童労働の暗喩。教育どころじゃねぇ。
「自分で考えない」ってだけで破滅する構造
ピノキオの特徴って、実は悪意が一切ないところ。
素直で、人の言うことを全部信じる。
でもそれが逆に、詐欺師たちの思うツボになる。
「だまされやすい=選べない=破滅まっしぐら」。



子どもは善悪の判断ができないから、ちゃんと教えられないとダメっていう、教育の恐怖。
ジミニー・クリケットが必死に止めても聞かないあたりも、「親や教師が見本になれば子は育つ」って信じたいけど、現実は甘くねぇって描いてる。
声で泣かすな。ジミニー=肝付兼太の破壊力
これ日本語版限定の話だけどさ、ジミニーの声が大山のぶ代版のドラえもん・スネ夫でおなじみの肝付兼太さんなのよ。
この時点で団子的にはもうエモMAX。
しかもその声が、ピノキオを守る良心の象徴なんだよ。



要するに「スネ夫が本気出すとめっちゃ頼れる」ってこと(?)
ゼペットじいさん、不死身説
これも地味に話題になるけど、ゼペットじいさんの生命力おかしすぎないか?
まず、自分で作った人形が喋り出しても秒で受け入れる柔軟性がすごい。
その後、行方不明になったピノキオを探すために自ら海へ船を出して、気づいたらクジラの中で生活している。



もはやこの人、「親」っていうより勇者だろ。
ピノキオが成長の物語を歩んでいる一方で、ゼペットは無条件の愛という名の不死身ぶりを見せてくれる。
この作品、父性強すぎ。
🍡焦げ団子の映画感想一覧🍡
→https://kogedango.com/movie-list/
ディズニー映画『ピノキオ』(Pinocchio)|考察
ピノキオは”利用される子ども”のメタファーだった?
「プレジャー・アイランド」は、ただの悪い子を反省させる施設なんかじゃない。
実際には、子どもたちを都合よく操り、思考を止めさせ、最終的にはロバに変えてしまう。
そんな恐ろしい場所として描かれている。
ロバになった子どもは意思も言葉も奪われ、泣き叫ぶことしかできなくなる。
これはまさに「自分で考えないで流されると、誰かの都合のいい存在にされてしまう」という寓話的な警告だろう。
当時の社会背景を考えると、「子どもが小さな労働力として扱われる」のは珍しい話ではなかった。
貧しさや教育機会の欠如、親が子どもに十分に目を向けられない状況が重なれば、子どもは無知のまま成長し、搾取されやすい立場に置かれてしまう。
ピノキオの物語が突きつけてくるのは「無知のままでは、社会の歯車として利用されてしまう」という厳しい現実。
ロバにされるという表現は、従順さと声を奪われることの象徴だったのだと思う。
「愚か=従順な労働力」という世界
ここで描かれているのは、「学ぶ機会がない子どもは、社会の中で都合よく扱われてしまう」という、なかなかにシビアな構造だ。
ロバになるというのは、自分の意志を失い、声も出せなくなって、ただ命令に従うだけの存在に変えられてしまうこと。
つまり「何も考えないまま生きること」が、誰かにとって都合のいい状態になってしまう。
戦時中〜戦後の時代背景を考えれば、「子どもが早くから働かされる」なんて話は珍しくなかった。
貧しい家庭、教育の機会がない状況、親の不在──そんな中で、「勉強よりもまず生活のために働かなくてはならない」子どもがたくさんいたのも事実だ。
ピノキオは、そうした知らないままでは自由を失うという構造を、寓話として浮かび上がらせた物語なのかもしれない。
サーカス団=見世物にされる子ども
ピノキオが連れていかれるサーカス団には、ちょっとした恐ろしさがある。
彼が“操り人形”として扱われるのは、まさに「言いなりで従順な存在」としての象徴。
たしかに、人形が踊って歌えばウケはいい。
でもそれって、子どもが大人の娯楽のために利用されている構図でもある。
現代で言えば、SNSで子どもの映像が使われることや、芸能の世界で子どもたちの環境が注目されるような問題とも、どこか似ている。
それが1940年のアニメですでに描かれていたと気づくと、なかなかに考えさせられる。
ピノキオ=流される子ども像
ピノキオが“悪い子”だったわけじゃない。ただ、何も知らなかっただけ。
誰を信じていいかもわからず、目の前の楽しそうな誘いに飛びついた──その結果、思いがけない世界に飲み込まれていく。
この物語にあるのは、「無知や未熟さにつけこまれる危うさ」。
流されるだけでは、自分の身を守ることができないという現実。
だからピノキオは、ただの道徳教育の話ではない。
「自分で考える力がないと、知らないうちに望まない場所に連れていかれてしまう」という、すごく現代的なテーマを内包している作品でもあると思う。
ディズニー映画『ピノキオ』(Pinocchio)まとめ:この頃のディズニー、闇が深すぎる
『ピノキオ』はディズニーの中でもかなりダークな空気をまとってる。
誘惑・操作・誘導・変身・役割の押し付け…どこを切ってもゾワっとくる要素だらけ。
しかもそれを「立派な人間になるため」って名目で描いてるのが、結構怖い。
あれって子ども向けのふりして、
「ちゃんとした人間にならなきゃ」っていう価値観を刷り込む教育アニメだったのかも?



ディズニーのファンタジーって、笑顔の下に深い闇が眠ってる。
その他のディズニー作品もレビューしてます
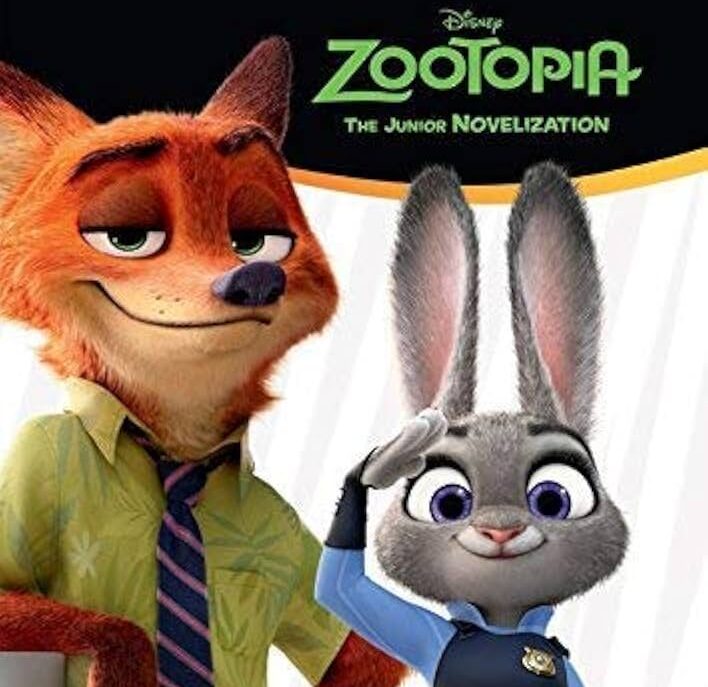
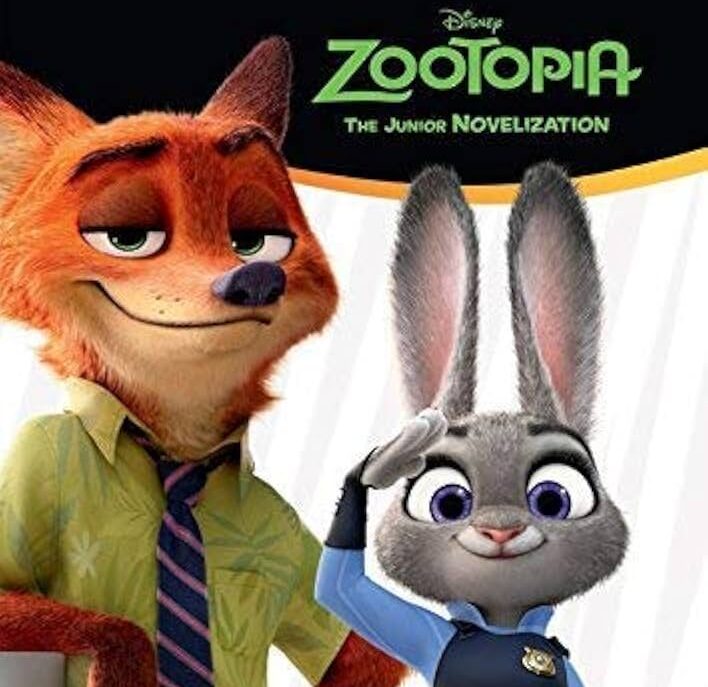


その他ピクサー作品も!
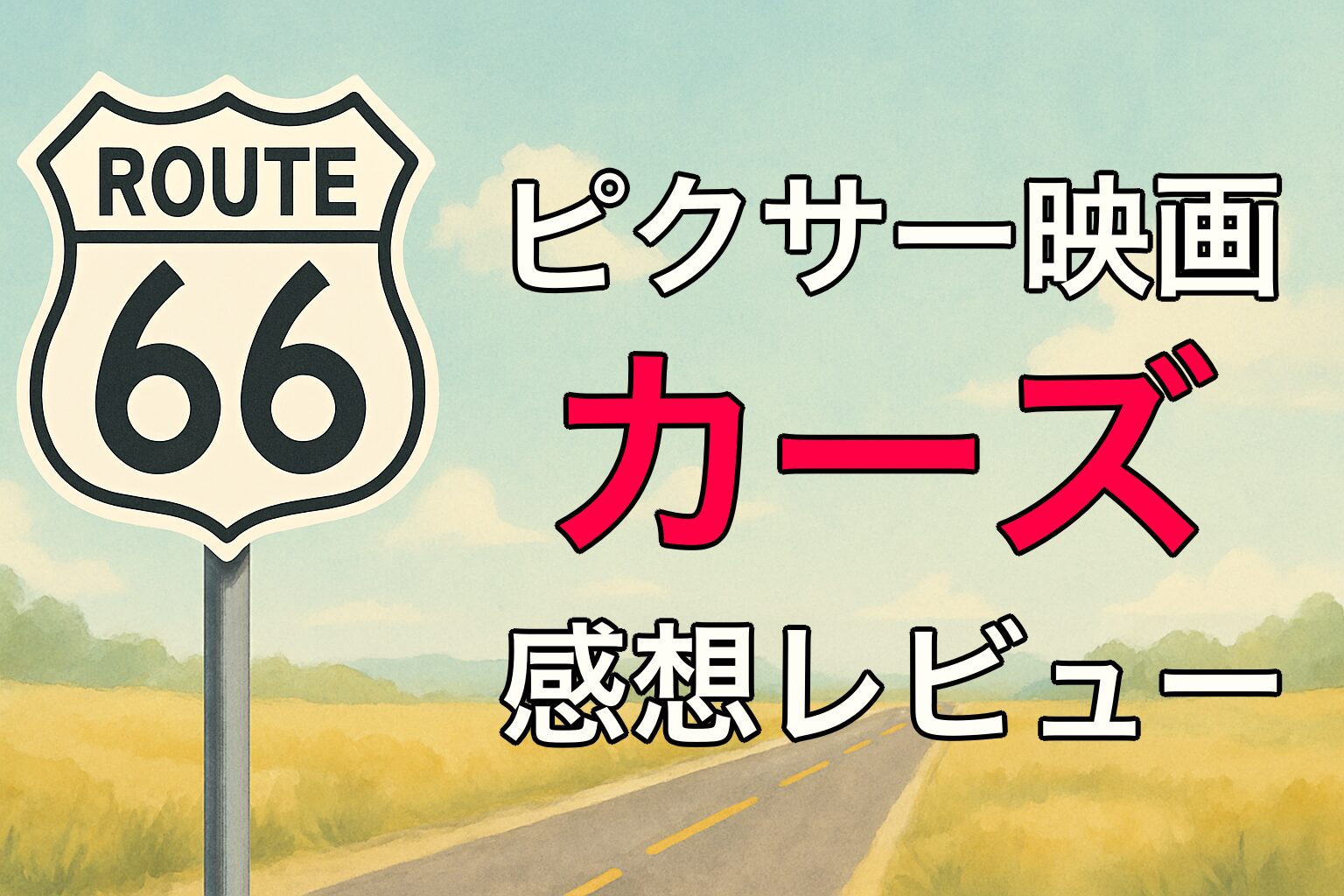
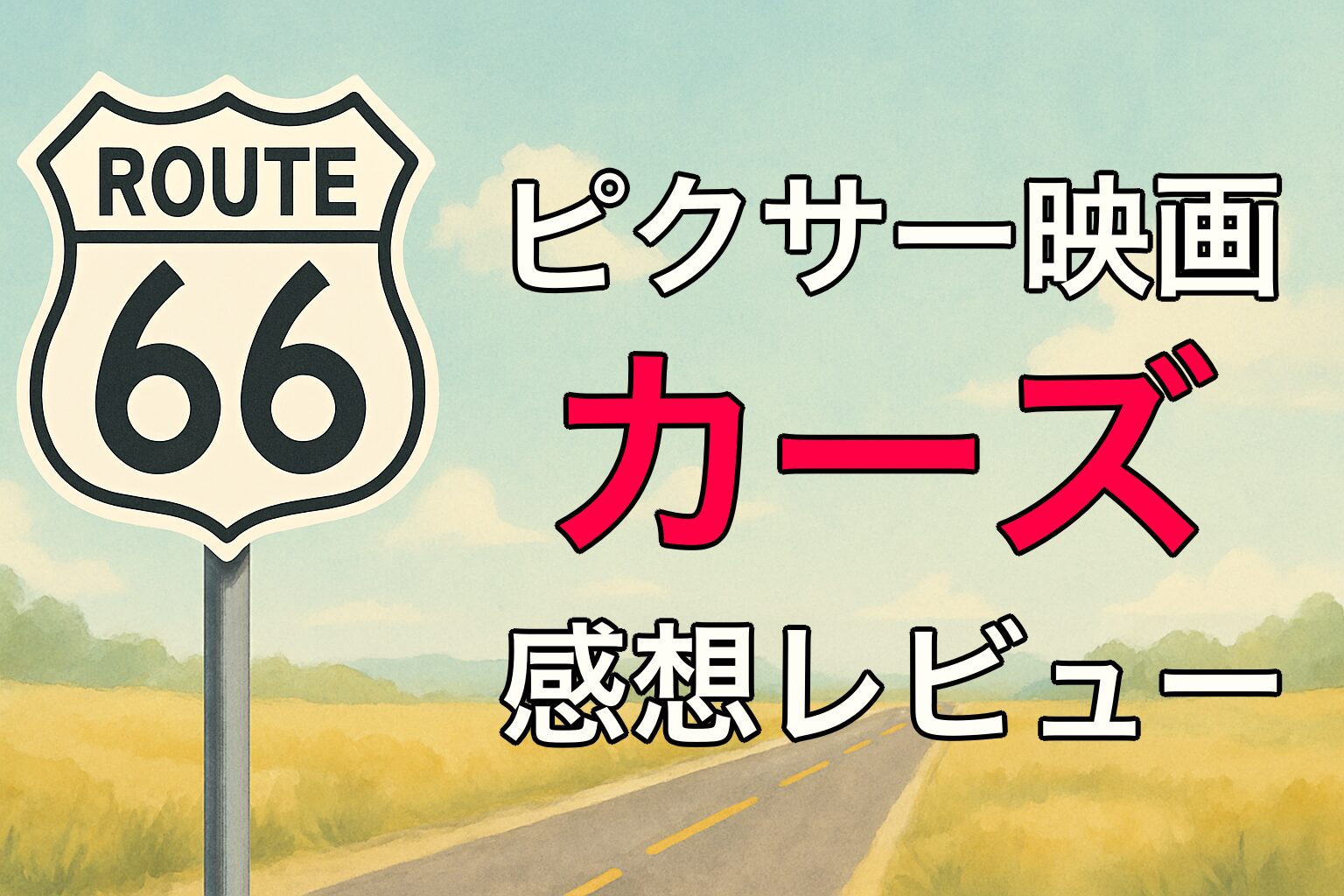
映画カテゴリの最新記事