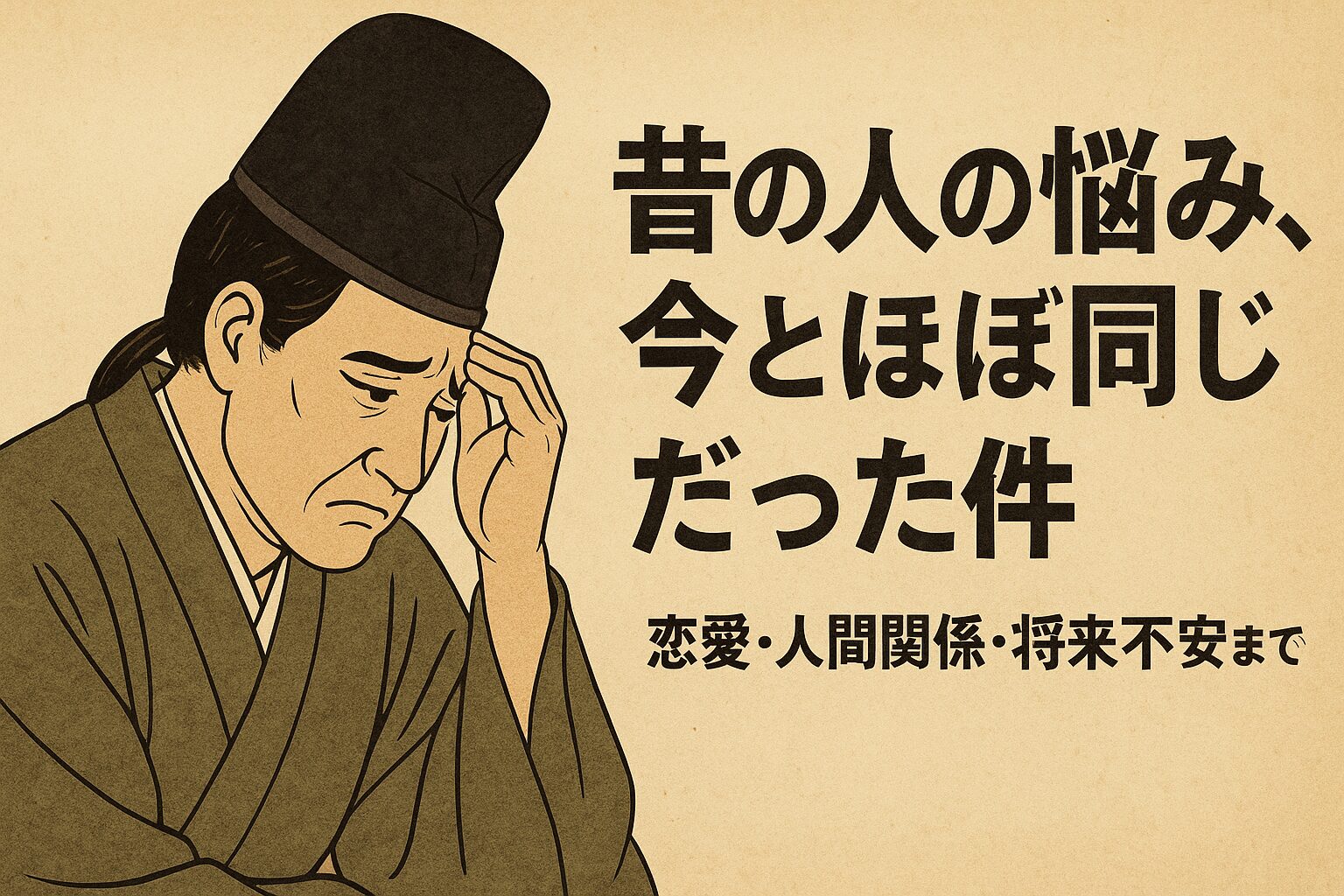焦げ団子
焦げ団子昔の人って、もっと悟ってたんじゃないの?
恋も人間関係も、生き方そのものも。
どこか静かで品があって、今みたいに“メンヘラ”だの“既読無視”だのとは無縁だった──はず。
…と思ってたんだけど、ちょっと古典を読んでみたら様子がおかしい。
——要するに、全部こっちと同じだった。
「平安時代の貴族」とか聞くと別世界の人みたいだけど、やってることは“LINE返ってこない”で病んでる大学生と変わらない。
というわけで今回は、昔の人たちがどんなことで悩んでいたのかを見ていく。
冷静に、淡々と、ちょっと鼻で笑いながら。
団子の人間関係のお悩みもぼやいてます


恋愛に悩むのは平安時代もデフォだった


昔の人って、もっと達観してるかと思ってた。
恋も悟ってて、和歌で「風情がどうの」なんて言って、情を交わしてたんだと思ってた。
——実際のところ、やってるのはほぼ既読スルーと温度差ゲームだった。
清少納言、「一晩で帰る男」にキレる
枕草子にはこうある。



男が一晩来て、朝には帰ってしまうのは腹立たしい
by 枕草子
なるほど、つまりやり逃げはNGってことらしい。
今風に言えば「また連絡するね」も言わずに消える男にブチギレてる状態。
千年前から、律儀に帰る男は地雷扱いだったようだ。
紫式部の“拗らせ日記”が現代のポエムすぎる



女は好きって言われたら本気にしてしまう。
でも男はすぐ飽きる
……これが1000年前の知見だ。
さすがにそろそろ改善してるかと思いきや、2025年現在、状況はほぼ変わっていない。
むしろ、言葉に責任を持たない男は現代でさらに進化し、
「“好き”って言ったけど付き合うとは言ってない」とか言い出すようになった。



釣った魚には餌をやらないというやつですか。
和歌にも既読スルーが存在していた話
当時の恋愛は、和歌で始まり和歌で終わる。
だが、返歌(へんか)が来なければ、それで終わり。



この気持ちは風に散るばかり…
返ってこないメッセージに詠むのがこれ。いわば和歌版の“未読スルー”ポストである。
しかもこれ、一週間とか平気で放置される。
恋愛において、スピード感が求められるのは令和も平安も同じらしい。
ちなみにこの時代、LINEも既読もないけど気配をスルーされた感はしっかりあったらしい。



つまり魂の既読無視ってやつ。
当時の恋愛に必要だったのは、文才でも教養でもなく、スルースキルと耐久力だった。
言葉の表現が上品なだけで、やってることは今と変わらない。
——恋愛は昔からずっと面倒くさい。
それだけは確か。
人間関係のストレス、千年前からしんどい
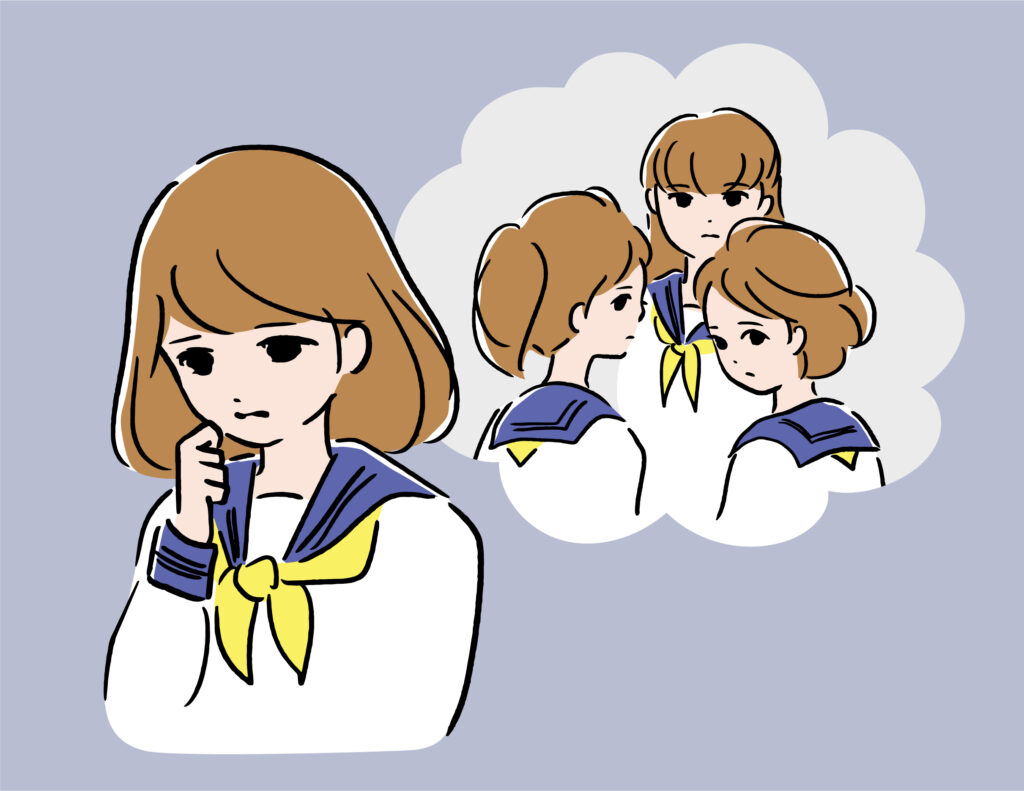
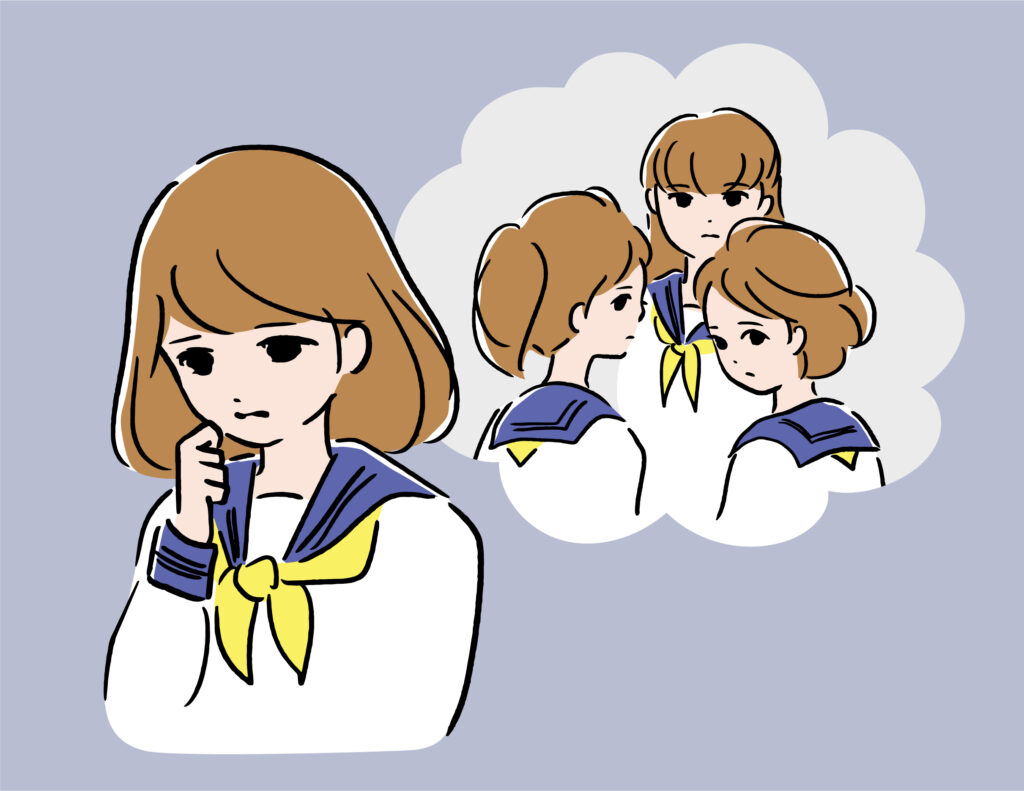
「昔の人は心が穏やかで、人付き合いも丁寧だった」みたいな幻想、そろそろ捨てていい。
むしろストレスの質は現代より面倒くさいまである。
空気も読まなきゃいけないし、身分の差もあるし、そもそもネットがない。
つまり、愚痴る場所もないのに我慢だけは強制される世界だった。
枕草子は「無理な人あるある」の宝庫だった



話がつまらない人は時間の無駄



噂話しかしない人、うんざり



声が大きいだけで偉そうにする人は、だいたい偉くない
•••以上、清少納言さんの愚痴三連発。
こんなのわざわざ書き残してるあたり、だいぶたまってたのは間違いない。
あとから「風情がない人は好きじゃない」とか言葉を柔らかくしてるけど、やってることは陰口ノートそのもの。
たぶん現代にいたら、「○○な人あるある10選」とかブログに書いてる。
しかもタグに「#愚痴じゃないです」ってつけるタイプ。



なお、本人はそれなりに社交的だった模様。
戦国武将も、裏切りと陰口に疲れていた
とある武将の手紙には、こうある。



味方のふりして裏で文句言ってくるやつがいて、つらい



忠義ぶってたくせに裏切るやつ、どうにかならないのか
内容はだいぶ切実。
味方が敵になるのも当たり前だった時代だから、信頼関係とかあってないようなものだった。
忠義は建前、腹の中は地雷。
Teamsで既読だけついて返事がない、みたいなもん。



戦より“人間のほう”で気に病んでるの、ちょっと笑えない。
江戸の町人、近所づきあいに病んでいた記録あり
日記の中にこんなのがある。



挨拶をしなかったと文句を言われた



井戸の使い方が汚いと怒鳴られた



子供の声がうるさいと文句が来た
見事に現代の集合住宅あるある。
掲示板も自治会もなかったぶん、いちいち口頭でクレームが飛んでくる。
今ならSNSに「隣人ヤバい」と書いて済ませられるけど、当時は全部リアル通報。
平和そうに見える江戸の暮らしも、蓋を開けたらわりと刺々しい人間関係で成り立っていた。
結論として、人間関係のストレスは、いつの時代も人類に共通のバグだったらしい。
文明が進化しても、人間のコミュニケーションスキルは大して変わってない。
むしろ今の方が距離の取り方に慣れてるぶん、マシな面すらある。
まあ、どっちにしろしんどいけどね。
体調不良とメンタルの落ち込みは、昔もよくある話


健康法とか養生訓とか、昔の人ってやたらと元気に生きることに必死だったけど、その裏では普通に体調崩して寝込んだり、意味もなく落ち込んだりしていたらしい。
言い換えると──
「不調の原因がわからないけど、なんか全部つらい」って状態は、わりと千年前からデフォだった。
「今日は気分が沈んでいる」って書き残す平安貴族
某貴族の日記にはこういう記載がある:



風の音がうるさく、眠れず、心が晴れないまま朝を迎えた
…うん、完全に寝不足のメンタル落ち。
現代人なら「イヤホンつけてYouTube流して無理やり寝た」って書きそうな状況。
それを「風のせい」にしてるあたり、ちょっとだけオシャレに病んでて逆に怖い。
何もせず布団にくるまる貴族
また、とある貴族の日記によると、



本日は気が重く、仏にも参らず、何もせず布団に伏した
いわゆる寝逃げ。
寝れば全部どうでもよくなると思ったのかそれとも本気で体を壊してたのかは不明だけど、気が重いから今日は無理って判断を言語化してるのはすごい。
むしろ団子は「今日も気が重かったけど、それすら忘れて過ごした日」があるので、ちゃんと自覚して記録してる時点で平安貴族のほうが自己管理うまい説ある。



何もせず布団にいる日を“怠惰”と言われがちだけど、
平安人がやってると“風流”になるらしい。
「仏の声が遠く感じる」とかいう詩的すぎる病み方



仏の声が遠く、光も差さず、心の内は暗し
……これはもう、ポエムという名の絶望。
ありがたい言葉すら届かなくなるとき、人はとにかく言葉を並べて存在を確かめたくなる。
そしてだいたい、そのまま寝る。
要するに、気圧が低い・なんかダルい・気がついたら夕方だったみたいな現象は、人間の仕様としてかなり初期から搭載されていたっぽい。
今みたいに「メンタルヘルス」なんて言葉もなければ、病院もなければ、休職制度もない。
それでも、なんとなく不調を感じて布団にくるまっていた人たちが確かにいた。
その記録が1000年後に読まれてるんだから、団子が今日寝てたことも、わりと肯定していい気がする。
将来への不安は、もはや人類の初期設定


未来に希望を持っていたかといえば、そうでもなかった。
むしろ「この先どうなるのか分からない」「何のために生きてるのか分からない」と言って、漠然とした不安に飲み込まれていた人は、普通にいた。
時代が違うだけで、考えてることはこっちとほぼ同じ。
平安貴族、「人の世は儚い」ばっかり言ってる
枕草子、徒然草、方丈記──
出てくるたびに「この世は無常」「人生は泡のよう」って言ってる。
冷静に考えると、しょっちゅう病んでる人の言動とほとんど一致している。
「また来世で」とか「この世は仮の宿」とか、やたらと来世に期待してるのも特徴。
現代で言えば、「異世界転生してやり直したい」ってツイートと同じ構造。
千年前の日本は、だいぶ異世界願望に包まれてた。



つまり希望という名の現実逃避。
農民、「来年の米がとれなかったら詰む」と怯えていた
年貢制度のせいで、「今年も収穫が少なかったら首が飛ぶ」みたいなプレッシャーが常にあった。
しかも天候は運任せ。どんなに頑張っても、干ばつや虫で一発アウト。
将来への不安というより、数ヶ月先の命が保証されてないという状態。
そのわりに村単位で「助け合いましょうね」みたいな仕組みが少なくて、各自でなんとかしなきゃいけないという闇。
今で言うと、生活費ギリギリのフリーランスがインボイス制度で詰んでる感じに近い。



ちなみに米が不作でも年貢は減らなかった。
それもう実質サバイバルゲーム。
幕末の志士、「国ごと終わるんじゃないか」と思っていた
黒船が来て、外国が開国を迫ってきた頃、「このままだと日本が滅びる」と書き残した人が何人もいた。
つまり「この国、もうダメかもしれない」っていう空気感は、Xだけの話じゃなかった。
むしろ当時は、そう思ったらマジで戦が始まってたので、リアルが重い。
今も昔も、「このままで大丈夫なのか」「全部崩れるんじゃないか」っていう不安はある。
経済でも政治でも人間関係でも、ちょっとしたことで何もかも崩れそうな感じは、昔からずっと付きまとってる。
それでも、なんとか生き延びて、こうして記録を残した人がいた。
団子もこうしてブログを書いてる。
つまり、不安はあっていい。むしろ、あるのが普通。
まとめ:何も変わらないまま、人間はここまで来た
平安時代の貴族も、江戸の町人も、幕末の志士も、戦国の武将も──
結局みんな、悩んで病んで、将来にビビってた。人間は1000年経っても、何も変わっていない。
そして千年前の不安も、こうして誰かが拾い上げて笑いに変えていること。
だから団子も、今ある不安をこうして文字にして焦がしておく。
きっとまた、誰かがそれを見て、「昔の人って、案外わたしと変わらないんだな」って思ってくれる気がするから。



団子も焼き直しながらここまできた。



焦げ目があるぶん、味はあると信じたい。
団子の人間関係のお悩みもぼやいてます