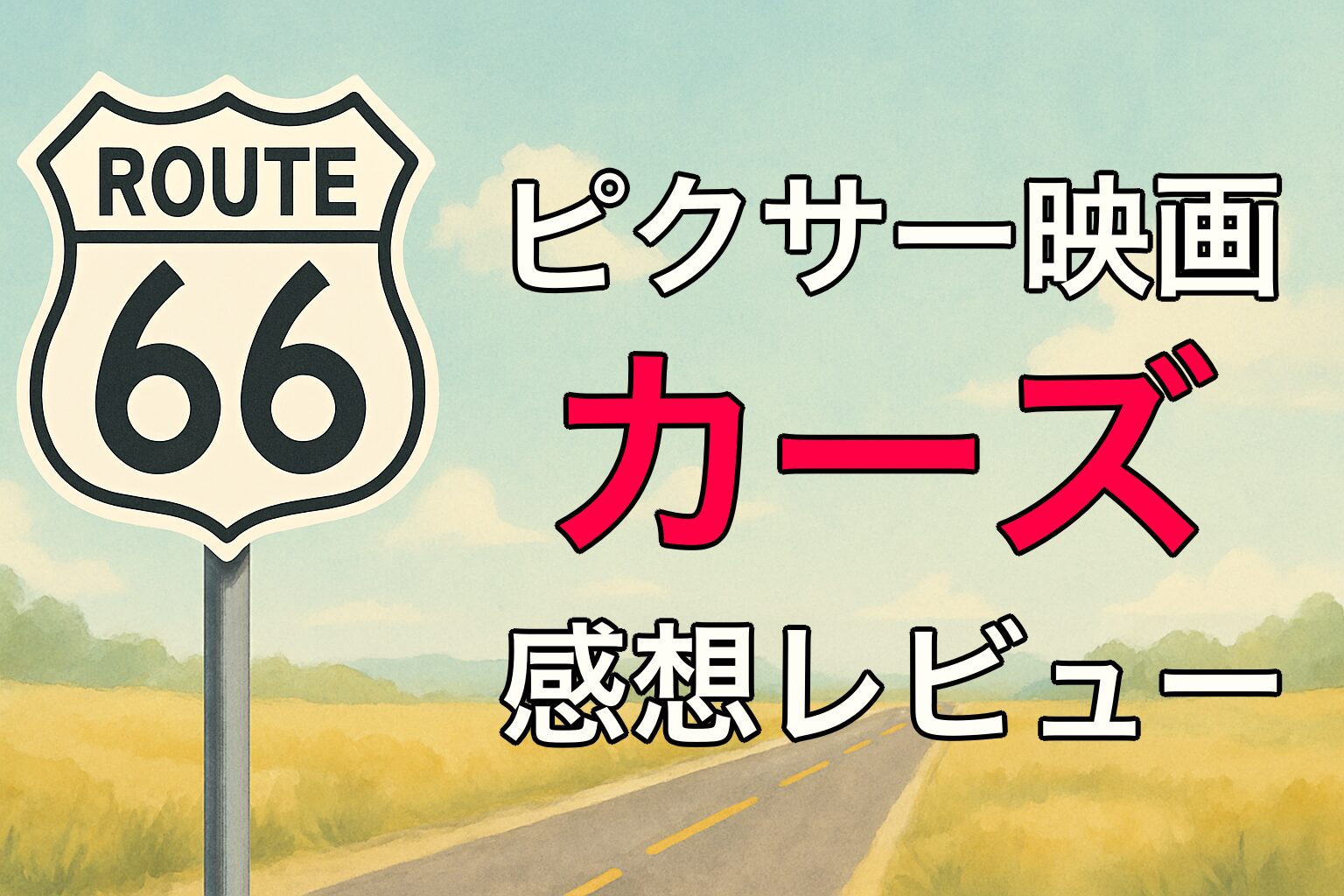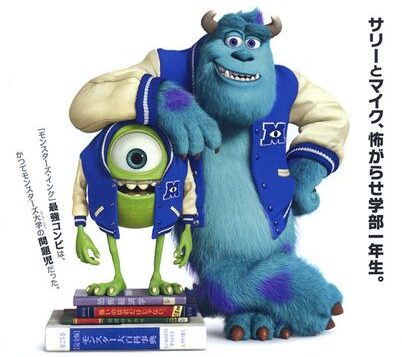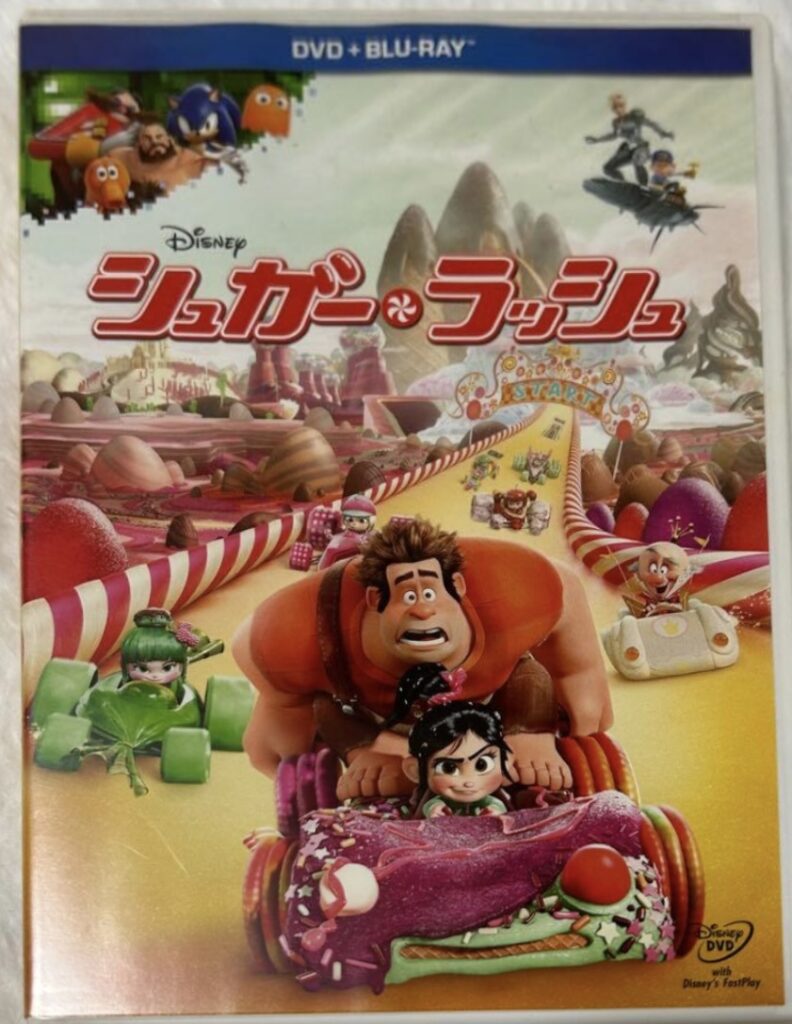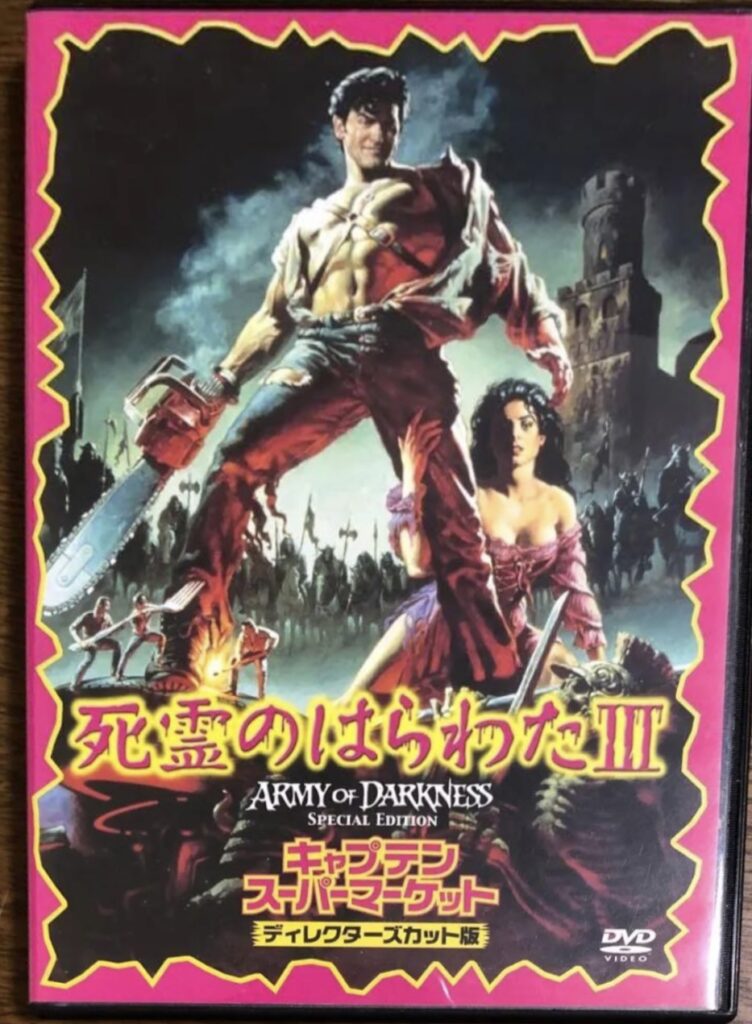『カーズ』は、ディズニー&ピクサーが2006年に公開したアニメ映画。
車たちが人間のように暮らす世界で、レースに人生をかける1台の車が主人公だ。
その名は、ライトニング・マックィーン。
若くして注目される天才レーサーで、スピードと栄光がすべてだと思って生きている。
だけど、とある田舎町に迷い込み、個性的な住人たちと出会うことで、“成功ってなんだろう?”と問い直す旅が始まっていく。
この映画、表面だけ見るとただのレースものに見えるけど──
実は、マックィーンが自分の価値観をひっくり返されていくめちゃくちゃ人間くさい成長ドラマなのだ。
今回紹介するお話が載ってるブルーレイはこちら
カーズ(Cars)ネタバレあらすじ|スピードしか信じてなかった男が、知らない町で止まる話

天才新人レーサー、ライトニング・マックィーンは、ピストンカップというレースの年間王者を狙って大活躍中。
でも彼は自分だけの力で勝ちたいという野心の塊で、チームメイトにも冷たいし、協調性ゼロ。
決勝戦を前にして移動中、トレーラーから落ちてしまい、
ひょんなことからラジエーター・スプリングスという忘れられた田舎町に迷い込んでしまう。
しかも町の道路をぶっ壊した罪で、修復作業を命じられて足止め。
「オレを誰だと思ってるんだ!」とキレるマックィーンだったけど、のんびり生きる町の住人たち。
ポンコツだけどやたら人懐っこいレッカー車のメーター
昔は名レーサーだったけど今は黙って暮らすドック・ハドソン
落ち着きと芯の強さを持つ女車(ヒロイン)サリー
そんな連中と過ごすうちに、少しずつ彼の心に変化が現れていく。
やがて町を離れ、レースに戻ったマックィーン。
最後の勝負の舞台で、彼が選んだのは──
「勝つこと」じゃなく、「誰かのために止まること」だった。
ディズニー&ピクサー映画カーズ(Cars)|考察&感想

走り続けるしかなかったマックィーンに、共感しすぎてしんどい
ライトニング・マックィーンって、最初はまさに「勝つことがすべて」っていう性格だった。
勝ってなんぼ。注目されてなんぼ。肩書きも実績も、とにかく派手で目立つものが正義。
……正直、自分にもそういう時期があった。
「派手な経歴」「評価される仕事」「すごいと言われること」
そういうものを無意識に追いかけてたし、自分は止まっちゃいけない側の人間だって思ってた。
でもこの映画、真逆を突いてくる。勝つことを捨てても、誰かのために立ち止まること。
目立たなくても、自分の場所で誇りを持って生きてる人たちがいること。
そういう地味だけど確かな幸せが、ずっと描かれてる。
で、ラストのレース。
優勝できるチャンスが目の前にあるのに、マックィーンは止まる。
「速く走ること=価値」だった彼が、“止まる”ことに価値を見出せるようになった瞬間。
これ、派手さや肩書きじゃなくて、「自分が何を選ぶか」で人生の意味をつくっていくってことなんだよな。
派手な世界・人間関係は、都合が悪くなるとすぐに消える
マックィーン、最初のレースではカメラに囲まれて、ファンに名前呼ばれて、誰からもチヤホヤされてた。
レースで勝てば大騒ぎ、でも離れたら一気に空気が変わる。
スポンサー候補も「別に君じゃなくていいんだけど?」みたいな顔してくる。
これ、現実でもめちゃくちゃあるやつだと思う。
- 会社辞めた瞬間、連絡してこなくなる元同僚
- SNSでバズってるときだけ絡んでくるけど、困ってる時は誰も見てない
- 「すごいですね!」って言ってた人が、調子が悪くなったらスッと引いていく
チヤホヤされてたのって、そのとき“価値がある人”だったからでしかなかったんだなって気づく。
マックィーンもそうだった。あの世界にいたとき、彼の周りにいたのは「その時、輝いてたから近くにいた人たち」だった。
東京タワーは、遠くから見てるのが一番綺麗

派手な場所・肩書き・交友関係は東京タワーみたいなものだ。
遠くから見てるうちはキラキラして見える。
でも、近づいて中に入ってみたら、案外そこには温かさも繋がりもなかったりする。
マックィーンは、ずっと「東京タワーの中」で勝負してた。
速く走ること、勝つこと、有名になること。それが価値だと思ってた。
でも、ラジエーター・スプリングスの人たちはちがった。
誰も彼をチヤホヤしないし、そもそも知らない。
でも、困ってるときには普通に手を貸してくれる。
肩書きとか関係ない。「そばにいるから、助けるよ」ってスタンスが当たり前の人たち。
派手な交友関係なんて、何かを持ってる自分にしか興味がない。
でも本当に大事なのって、自分がうまくいってなくても変わらず接してくれる人なんだよな。
そしてBGMがいちいち良すぎる
『カーズ』、実はサウンドトラックの完成度が異常。
ただの雰囲気BGMじゃない。
場面・感情・キャラの変化にピッタリ寄り添った選曲と作曲で、「音楽でストーリーが進む」レベルなんだよ。
「Real Gone」by Sheryl Crow(レース開幕!)
オープニングのレースシーンで流れるこの曲。
シェリル・クロウの疾走感MAXな歌声が、マックィーンの「俺がNo.1!」感を全力で煽ってくる。
俺が一番速い・勝てば注目される・派手な世界のスターだっていう世界観、セリフじゃなくこの1曲で説明されてるのがすごい。
「Life is a Highway」by Rascal Flatts(旅は人生)
『カーズ』を語る上で絶対に外せない曲、それがこの「Life is a Highway」。
日本じゃ“BGMのひとつ”って印象かもしれないけど、団子的にはあれこそマックィーンの人生そのものだと思ってる。
歌詞をざっくり意訳すると
人生は旅だ。
曲がったり止まったり、風向きに背を向けたりもしながら、それでも進んでいく。
いろんな街を通って、いろんな人と出会って「荷物は全部背負う。どんな道でも走り続ける」
最初は「俺だけの道」だったけど、途中で気づくんだよな。
誰かと一緒に走る旅の方が、ずっと意味があるって。
「Life is a Highway」って、物語が進むにつれて意味が深くなる曲なんだよな。
「Our Town」by James Taylor(取り残された町の哀愁)
来ました、全カーズ屈指の名シーン製造BGM。
この曲が流れるのは、ラジエーター・スプリングスの過去と現在を重ねる回想モンタージュ。
かつては観光客で賑わっていたのに、高速道路が通ってから誰も来なくなって、町はどんどん静かになっていく──
ジェームズ・テイラーのしっとりした歌声が、消えていく町の時間と、それでもそこにある人の営みをやさしく包み込んでて、団子的には毎回ここで涙腺終了。
Sh-Boom by The Chords(ネオンが灯る夜の蘇生)
マックィーンが町の道を自分で直して、かつての姿を取り戻した夜。
サリーやドック、みんなが集まって、あの静かな町がネオンで一気に色づく瞬間――
そこで流れるのが 「Sh-Boom」 by The Chords なんだよ!!!
まさにラジエーター・スプリングスが過去の栄光じゃなく“今も息づく町”として生き返る瞬間。
 焦げ団子
焦げ団子この場面があるからこそ、誰かと一緒に過ごすことが、マックィーンにとって意味を持ちはじめるんだ。
「Route 66」by Chuck Berry(王道ルートを外れた先で)
映画のテーマにもなってるルート66が舞台なだけあって、エンドクレジットではチャック・ベリーによる超王道アメリカンロック版が流れる。
マックィーンが目指してたのは高速道路なのに、最終的に「旧道(Route 66)」の方に心が惹かれてるって構造なんだよな。
音楽でもそれがしっかり表現されてるのがアツい。
今こそ観てほしい理由:映え文化まっただなかの現代に
今のSNSって、常に走り続けてないと取り残されそうで、映えとか承認とか、常にスピード・派手にが求められてる。
でも『カーズ』は真逆のメッセージをくれる。
「立ち止まってもいい」
「人目がなくても、ちゃんと生きてる場所がある」
ラジエーター・スプリングスは、忘れられた町なんじゃなくて、思い出すべき場所なんじゃないかと思う。
ディズニー&ピクサー映画カーズ(Cars)まとめ|止まることにも、意味がある
『カーズ』って、子ども向けのレース映画だと思われがち。
でも本当は、「止まること」や「人とつながること」の意味を教えてくれる、静かでやさしい物語だった。
若い頃って、スピード出すこと・派手に目立つこと・注目されること。
そんな「わかりやすい成功」がすべてに見えがちだ。
でも、マックィーンの旅はそれをひっくり返してくれる。
都会のきらびやかさに魅了され、勝利だけを追い求めていた彼が、何もない田舎町で出会った止まってくれる人たちに救われていく。
そして、自分も誰かのために止まれる存在になる。
これって、現代のSNS文化とか、走り続けなきゃ負けみたいな社会にこそ響くメッセージなんじゃないか。
派手じゃなくても、誰にも注目されなくても、そばにいてくれる人と、心から笑い合える時間こそが宝物なんだって。
他のディズニー映画についてまとめた記事はこちら!


映画カテゴリの最新記事