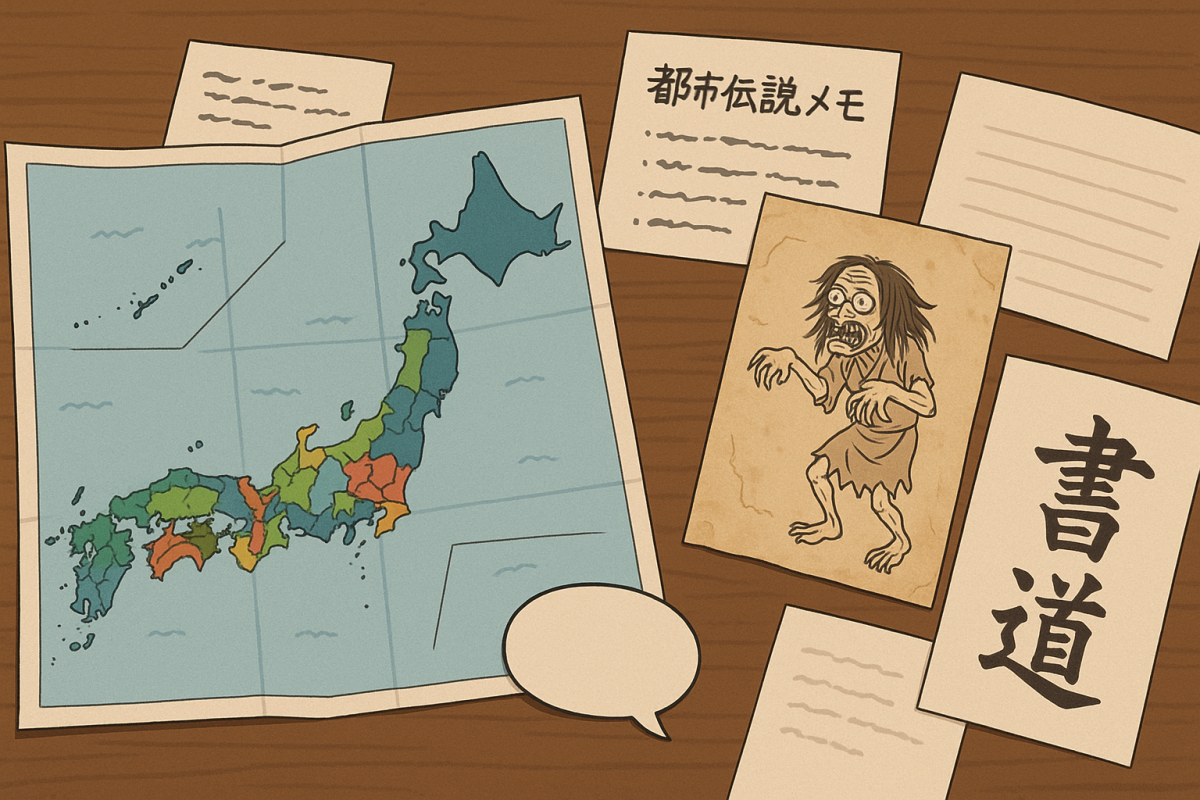「化かす」といえば、キツネとタヌキ。
昔ばなしでもアニメでも、だいたいこの2匹が変身キャラの定番枠を独占してる。
でもさ、冷静に考えてみたことある?なんでコイツらだけ、そんなに特別扱いされてんの?
しかも「人を騙す=悪役」のはずなのに、この2匹だけはなぜか愛されてるし、むしろちょっと憧れる存在になってたりもする。
今回はそんな化けキャラ界の2トップがなぜここまで定番化したのか、
そのルーツと理由を、団子的にちょっとひねくれた視点で掘ってみる。
歴史ってこんなにヘンテコで、こんなに面白かったっけ?
▼他にも“クセつよ文化史”ネタまとめてます。
文化史コラムまとめ一覧→焦げ団子がひもとく文化の断面図一覧
中国から来た妖狐 vs 日本生まれの化け職人
キツネ:中華生まれ、輸入型のエリート妖怪
キツネの妖怪ポジションのルーツは中国。
紀元前からある『山海経(せんがいきょう)』や、清代の怪談集『聊斎志異(りょうさいしい)』などに「九尾の狐」「美女に化けるキツネ」がガンガン出てくる。
つまりキツネは元々、神に近い何か+人を惑わす存在として長いキャリアを積んだ輸入エリート。日本に来てからは神格化ルートに分岐して稲荷信仰へ。「神の使い(眷属)」として、稲を守り商売繁盛まで担当。
でもその一方で、狐憑き=精神的に不安定な人を説明する便利ラベルとしても使われる。
つまり、日本に来てからのキツネは、
「神にもなれるけど、悪霊にもされる」
という両極端を生きる、超ハイスペック曖昧系キャラ。
タヌキ:完全和製、庶民派の妖怪職人
庶民文化が花開いた江戸時代。ここでタヌキは、妖怪というより笑いのわかる化け芸人みたいなポジションに定着していく。
たとえば、
- 人間に化けたのに、耳だけタヌキのままでバレるとか、
- 坊さんに化けて托鉢してたら、太鼓腹からポンポコ音がして正体がバレるとか、
- 街中で見かけたと思ったら、太鼓のようなお腹を叩いてリズム取って逃げていくとか…
もう完全に落語の登場人物。
「騙す」っていうより「ひと笑い取って消える」タイプのトリックスター。
江戸後期には浮世絵にも描かれるほどの人気キャラになっていて、特に「狸囃子(たぬきばやし)」なんて音ネタ妖怪にも派生。
つまり、タヌキは
化けるけど、基本バレる。騙すけど、憎めない。
そんなヘマしても生き延びる愛嬌の天才としての地位を確立した。
なぜ「騙される側」じゃなくて「騙す側」になった?――人間に近くて、都合がよすぎた2匹の話
キツネもタヌキも、野生動物なのにやたら人里に現れるタイプ。山に住んでるけど、畑とか道端で見かけることもある。
つまり人間にとっては、「あいつら、ギリ喋りそう」枠。他の動物よりもちょっと人間に近い存在に感じられてた。
さらに、変身・化けるって行為そのものも、昔は「怖さ」があったけど、だんだんユーモア枠に落ち着いてくる。
江戸時代の大衆文化(黄表紙や草双紙)では、
キツネ=色気のある美女に化ける
タヌキ=商人や坊主に化けて失敗する
みたいなテンプレが流行る。
騙すことで物語が動く。
でも最終的に笑えるオチになる。
そういう意味で都合が良すぎて、人間の「化かしニーズ」を一手に担う存在になっていった。
キツネ=女性像、タヌキ=男性像って決めたの誰?――色気と間抜けを勝手に性別で割り振った結果
気づけばこうなってるけど、別に誰かが決めたわけじゃない。
- キツネ=「狐の嫁入り」「狐火」→ 妖艶・不可解・美
→ミステリアス美女ポジションに自動配属 - タヌキ=「ぽんぽこ腹」「酒好き」「狸親父」
→ 俗っぽい中年男にキャラ付けされがち
でもそれ、冷静に言うと
勝手に「色気」と「間抜け」を性別に当てはめただけの偏見。
キツネもタヌキも性別関係なく化けてんのに、人間側が勝手にキャラの都合で属性を押し付けてきた結果がこれ。
日本人はなぜこんなに「変身キャラ」が好きなのか――本音と建前を生きる国の、正体バレ愛好癖
キツネやタヌキに限らず、日本の昔話・妖怪譚・アニメ・特撮……どこを切っても変身だらけ。
- 化け猫、化け蛇、女郎蜘蛛、のっぺらぼう、鵺(ぬえ)
- 能の「隠された本性を舞で暴く」展開
- 特撮ヒーローの変身!
- ジブリもポケモンも鬼太郎も、なにかしら「変わる」存在が必ず出てくる
■ なぜここまで“変身”が好まれるのか?
① 表と裏を分けて考える文化だから
日本の伝統文化には、「本音」と「建前」ってセットがある。
- 表向きには笑ってるけど、内心では怒ってる
- 外からは普通の人に見えても、家では別人格
- 神社では穏やかな神様、でも裏には荒ぶる側面がある
つまり、
「本当の姿は隠されてる」っていう前提が、もともと文化に根付いてる。
② 自分の中にも“変身願望”がある
人間だれしも、「今の自分じゃない何かになってみたい」って気持ちがある。
- 美人に化けたい
- 頭のいい人になりたい
- ちょっと悪いやつになってみたい
- 誰にも縛られず自由に生きる何者かになってみたい
変身キャラって、その人間の理想や闇を代行してくれる存在なんだよな。
人はミステリアスなものがすき
キツネやタヌキに限らず、「正体がわからない存在」って、やたら気になるよな。
怖いはずなのに、目が離せない。なんか見たくなる。
人ってさ、基本的によくわからないもの=ちょっと怖いと感じる生き物。
でも一方で、
「あの人、何か隠してそう」
「本当は裏の顔があるんじゃ…」
「絶対こいつ正体違うやろ」
って思うと、むしろ気になってしょうがなくなる。
化けキャラって、まさにそこ突いてくるんだよな。
「本当は何者なんだろう」っていう謎があって、バレそうでバレない、でもたまにポロッと化けが崩れる。
そのギリギリの線に、人間はめちゃくちゃ惹かれる。
人間って、わからないからこそ想像するって生き物。
で、「裏がある」ってだけで、一気に面白く感じる。
変身キャラが刺さるのは「本性バレる瞬間がいちばんドラマになる」って、本能でわかってるからなのかもな。
かわいくて賢そうで人間に近い――そりゃ化かされても許すわな
キツネとタヌキが化けキャラとしてここまで親しまれてきたのって、よく考えると、かなり都合のいい属性を持ってたから。
- 知性がありそうに見える(目が細くて、人間っぽい挙動)
- 人間の生活圏にそこそこ出没する(山と里をまたぐ距離感)
- 見た目がなんだか可愛い(とくにタヌキのぽんぽこ感)
→ つまり、ちょっと不思議だけど憎めないっていう、マスコット化に最適な三拍子がそろってた。
そのうえで、変身する=人間の妄想を全部のせできる土台まで持ってたわけで。そりゃ、キャラとして定着するよな。
でも――
一番怖いのは、化けてもいないのに、ふつうの顔して人を騙す人間だったりする。
っていう事実だけは、忘れちゃいけない。
歴史ってこんなにヘンテコで、こんなに面白かったっけ?
▼他にも“クセつよ文化史”ネタまとめてます。