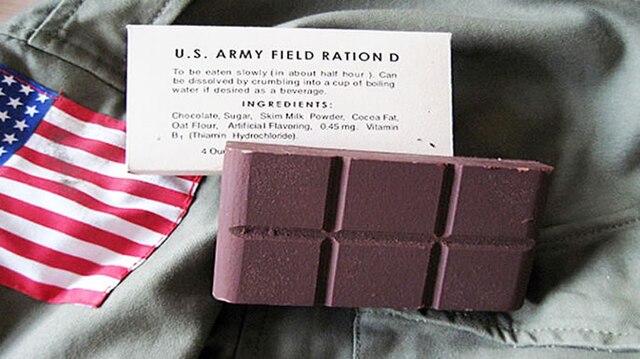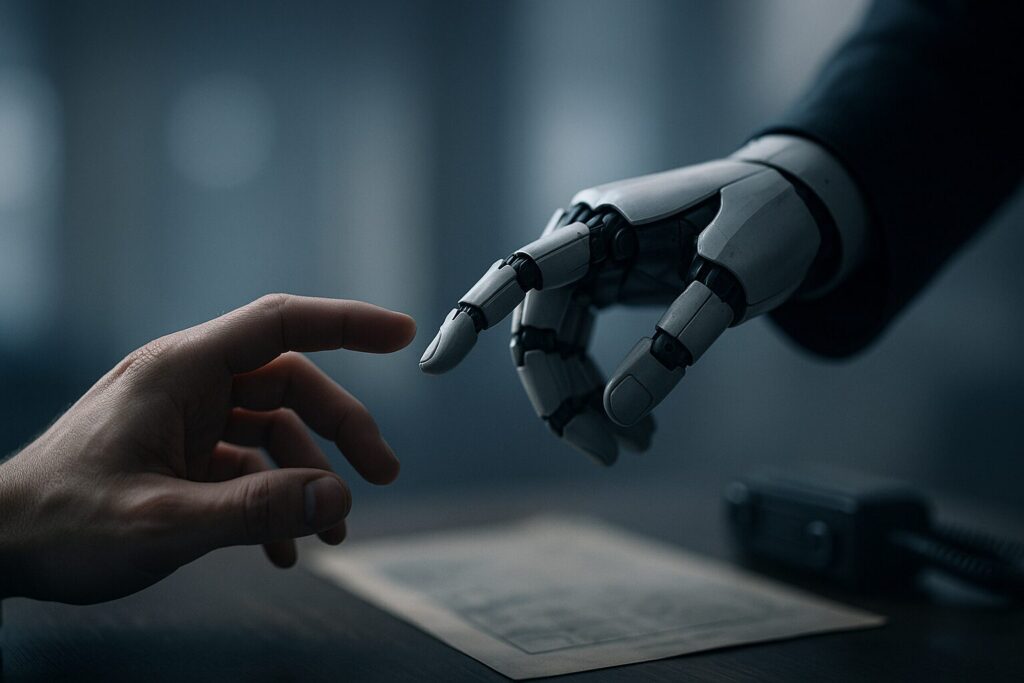2025年10月19日 、フランス・ルーブル美術館で、大胆すぎる宝石盗難事件が発生した。
そして──犯人が使ったのは、なんとドイツ製の建設用リフト。
……という無駄にプロ仕様な手口に加え、さらにSNSでは意外な展開が巻き起こる。
事件で使われたリフトが、ドイツの建設機器メーカー《Böcker社》製だったという情報が拡散されたのだ。
本来なら企業イメージに傷がつくはずの展開――
だが《Böcker社》は、その事実をまさかの形で逆手に取った。
\ 公式が事件をネタに広告を出す /
\ 「Wenn’s mal wieder schnell gehen muss.(急ぐならこれ)」爆誕 /
\ “静音・高性能”を堂々とアピールする逆張りマーケ爆走 /
 焦げ団子
焦げ団子おいおい、マジかよドイツ。
というわけで今回は、「ルーブル美術館の盗難事件に公式で乗っかってきたドイツ企業の逆張り広告戦略」を、焦げ団子的視点から全力でぶった斬っていこうと思う。
第1章:ルーヴル盗難事件Böcker社マーケティング|「犯人が使ったのはウチの商品」からの広告展開!?
ある意味で、これ以上ない実績紹介だったのかもしれない。
──フランス・ルーブル美術館での宝石盗難事件。
犯人グループが実際に使用したのは、ドイツの建設機器メーカー《Böcker社》のモバイルリフト。
あろうことか、現場に放置されたリフトの写真がSNS上で拡散され、その中にはBöckerの機器が堂々と写っているという信じがたい展開。
普通だったら企業にとっては完全に「風評被害」だ。
……が、Böckerはまさかの方向に舵を切った。
企業自ら事件に便乗。
事件後、Böcker社が公開した広告はこうだ。
なんと、事件に使われたリフトをモチーフにして広告を作成し、「Wenn’s mal wieder schnell gehen muss.(急いで移動したいときに)」というキャッチコピーとともに掲載したのだ。



こわいけど…なんか忘れられない!
Böcker社はこのブラックユーモア全開の広告を、実際にSNSで展開。
すると案の定話題となり、
やばい、これは記憶に残る…
正気かよ(褒め言葉)
といった反応が殺到し、この広告はInstagram上で約170万回リーチされ、通常の投稿(約2万回)に比べて実に85倍もの拡散力を記録したという。
つまり、「風評被害」ではなく「プロモーションチャンス」に変えたというわけだ。
第2章:ルーヴル盗難事件Böcker社マーケティング|炎上しない不謹慎広告はどこまで許されるのか?
今回のBöcker社の広告が話題になった最大の理由。
それは——「不謹慎なのに、なぜか許された」というギリギリのラインを攻め切ったからだ。
SNSでは、
これ広告にするのはさすがに不謹慎すぎる
いやむしろセンスあるし、記憶に残ったから勝ち
という賛否両論の声が飛び交った。
普通だったら企業イメージを守るために隠すはずの話を、あえて表に出して、しかもブラックジョークとして広告に仕立てた。
ここで重要なのは、この広告が成立した条件だ。
成立条件1:「人的被害がなかった」こと
まず前提として――ルーブル美術館で起きた宝石盗難事件は、決して軽く扱えるものじゃない。
文化財・美術品という公共的価値を持つ宝石が盗まれた以上、フランス国家にとっての重大な損失であり、れっきとした被害が存在している。
だが同時に、この広告が炎上を免れた背景には、「人的な被害(死傷者や暴力)」が発生していなかったことも見逃せない。
犯人はリフトを現場に残すという漫画的なミスを犯し、その姿がSNSで拡散されたことで、「深刻だけど、どこかコミカル」という絶妙な空気感が生まれた。
そして企業側は、その空気感をすかさず読み取り、ブラックジョークとして広告に転用した。
成立条件2:「表現が上品だった」こと
キャッチコピーは攻めているが、直接的な表現は避けている。
「静かで滑らかな動作」という製品の特長を、ブラックに皮肉っただけで、決して犯罪を肯定したり、被害者を笑ったりはしていない。
その結果、「ギリギリだけど笑える」というポジションを保つことができた。
つまり、炎上しない不謹慎にはルールがある。
- 被害者を笑わない
- 社会正義を踏みにじらない
- あくまで自虐や機転で乗り切る
この3点さえ守れば、むしろブランドイメージを強化する材料になる。



不謹慎と炎上の境界線で踊れる企業こそ、SNS時代の勝者になる!
成立条件③:「コミカルな要素が話題化したこと」
犯人が使用したと思われるリフトが現場に堂々と残されていたという点が、SNSで注目された。
この偶然が「Böckerのロゴが写ってた!」「あの広告は皮肉すぎる!」と、ブラックユーモアの文脈で消費される下地になったのかもしれない。
ルーヴル盗難事件Böcker社マーケティング|焦げ団子的考察——この事件が突きつけるマーケのジレンマ
SNS時代、企業が話題になるために越えなきゃいけないラインはどんどん上がっている。
目立たなきゃ、忘れられる。誤解されても、思い出されれば勝ち——そんな空気すらある。
成立条件は、ギリギリ笑えるラインを踏み越えないこと。
今回のBöcker社の広告が成立した最大の理由は、人的被害をともなう事件ではなかったことにある。
もしこれが暴力事件だったり、怪我人が出ていたら、たとえ面白い広告でも確実に炎上していたはずだ。
今回は「美術品の盗難」という犯罪ではあったが、SNSでは「リフトを置いて逃げた犯人の間抜けさ」や、「製品名が拡散された」という構図がお笑い事件として消費されるかたちになった。
そのため、ブラックユーモアがギリギリの線で成立したと言える。
印象に残る広告=「嫌でも覚えること」
Böcker社の広告を見た人は、おそらく一生このリフトの名前を忘れない。
「静かで高性能な侵入ツール」として、良くも悪くも記憶に焼きつく。
現代の広告が目指すのは、品の良さじゃない。
脳内への滞在時間こそが、最大のKPIなのかもしれない。
今は「うちの製品、安全です」だけでは刺さらない時代だ。
「静かで、すばやく、目立たない」なんて説明は、普通に書いても誰も読まない。
でも泥棒が選んだ道具として語られると、一発で刺さる。



ネガティブな話題ですら、自分たちの文脈に引き戻す力があれば、ブランドのイメージは再定義できる。
ルーヴル盗難事件Böcker社マーケティング|まとめ
ルーヴルの強盗事件は負の出来事だった。
でも、そこから“語られるべき広告”を生み出した企業の嗅覚は、ただのリフト会社の域を超えていた。
「炎上しない不謹慎」なんて綱渡りのギャグ、誰にでもできるものじゃない。
たしかに日本で同じことをやったら即大炎上かもしれない。
でもこの「不謹慎ギリギリ×高性能アピール」のセンス、海外マーケならではの武器の使い方だよなあ……と、団子的には感心せざるを得なかった。



犯人が選んだ製品って、ある意味で一番リアルな信頼じゃない?
……まあ、使い方は絶対真似しちゃダメだけどな!!
この記事が面白かった人はこちらの記事もおすすめ!




海外カテゴリの最新記事