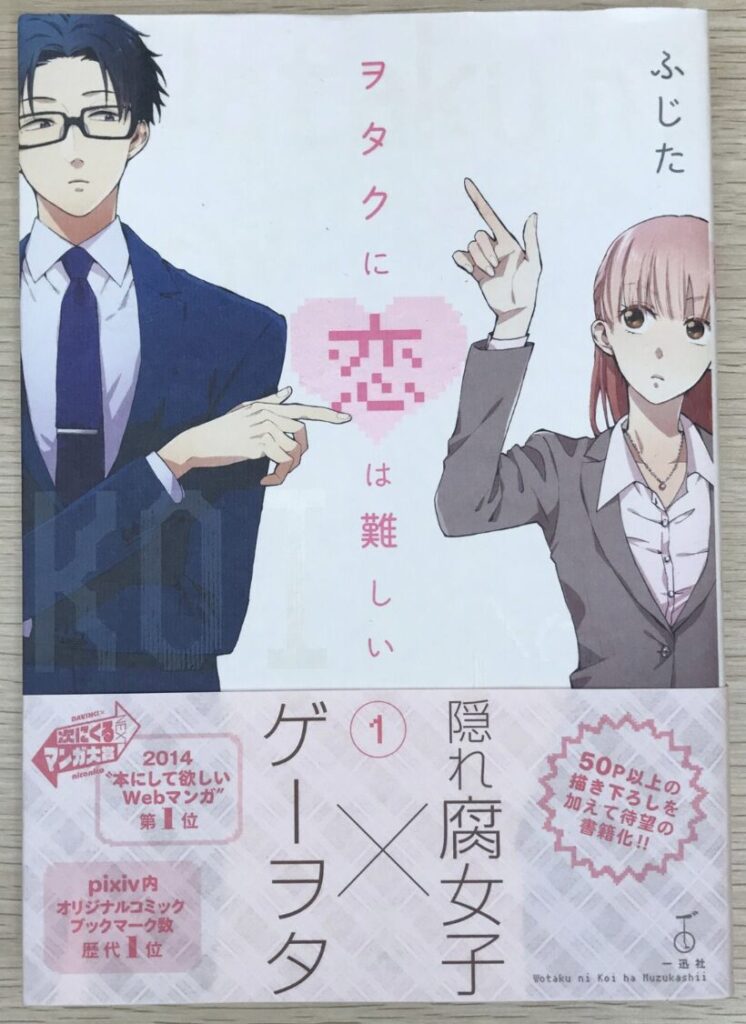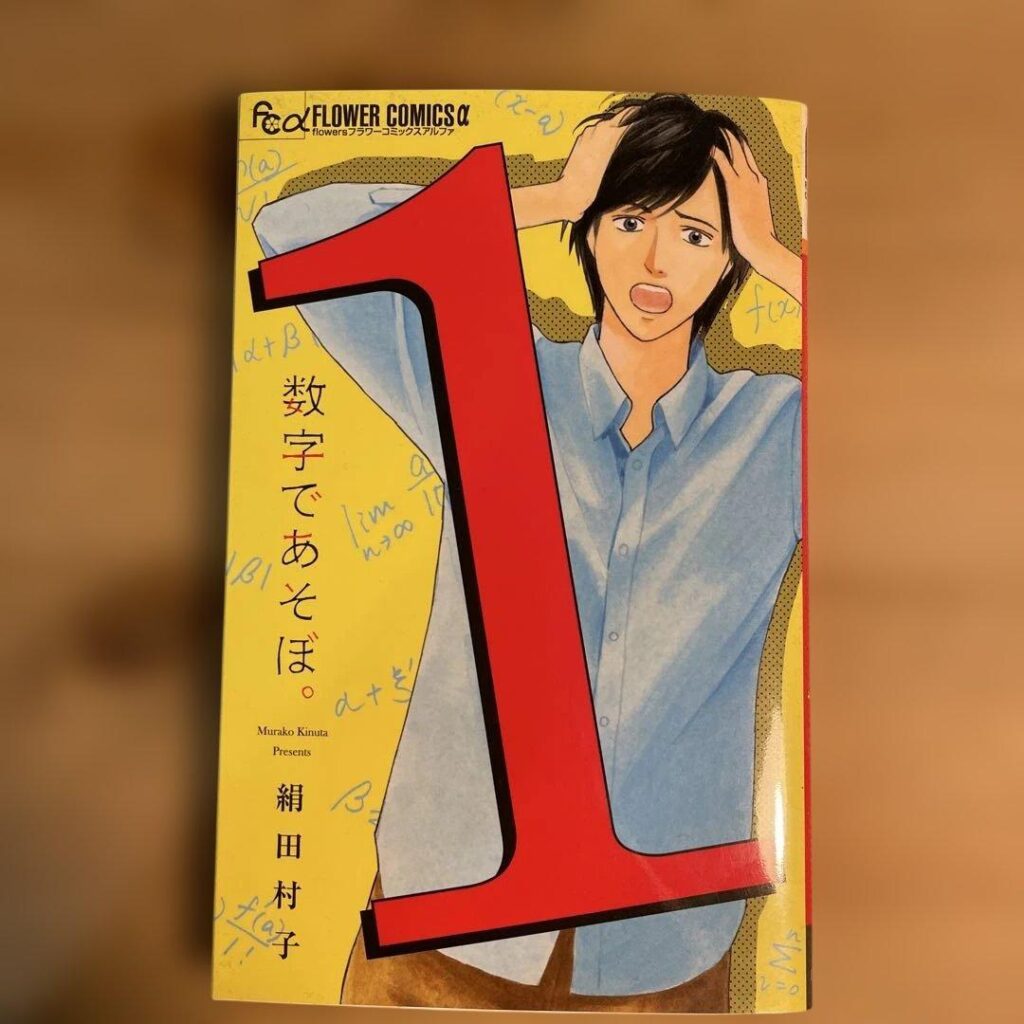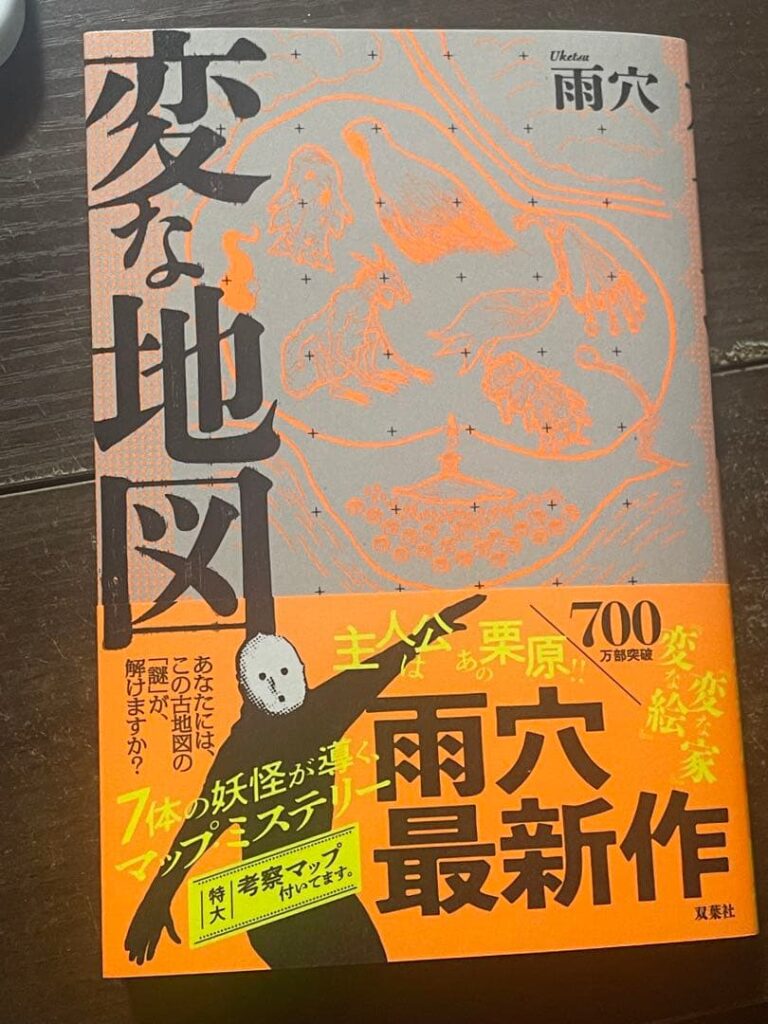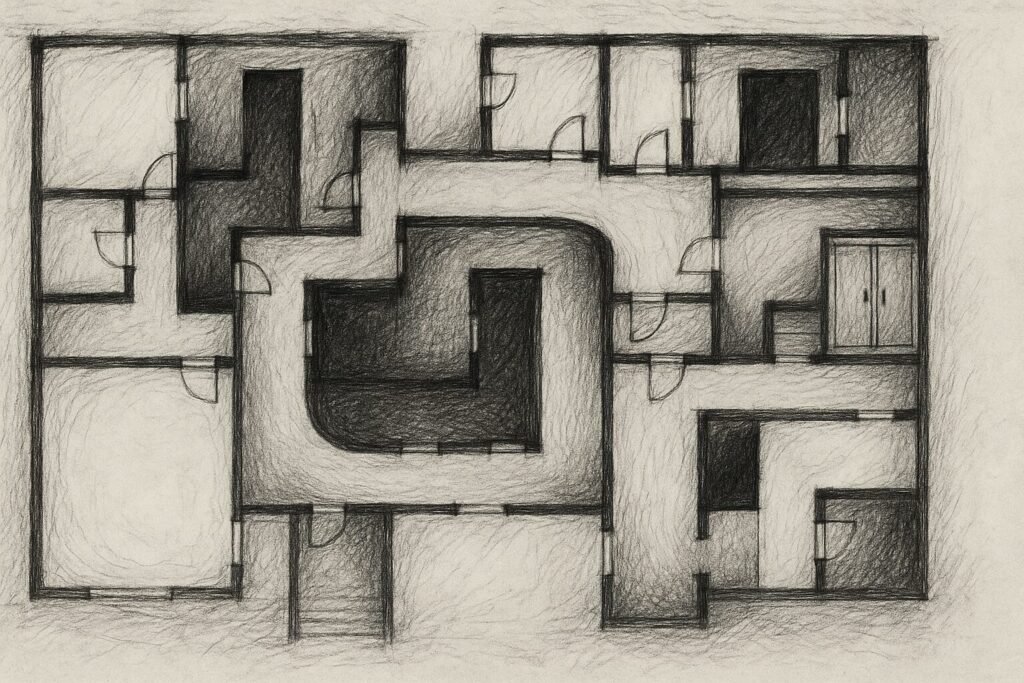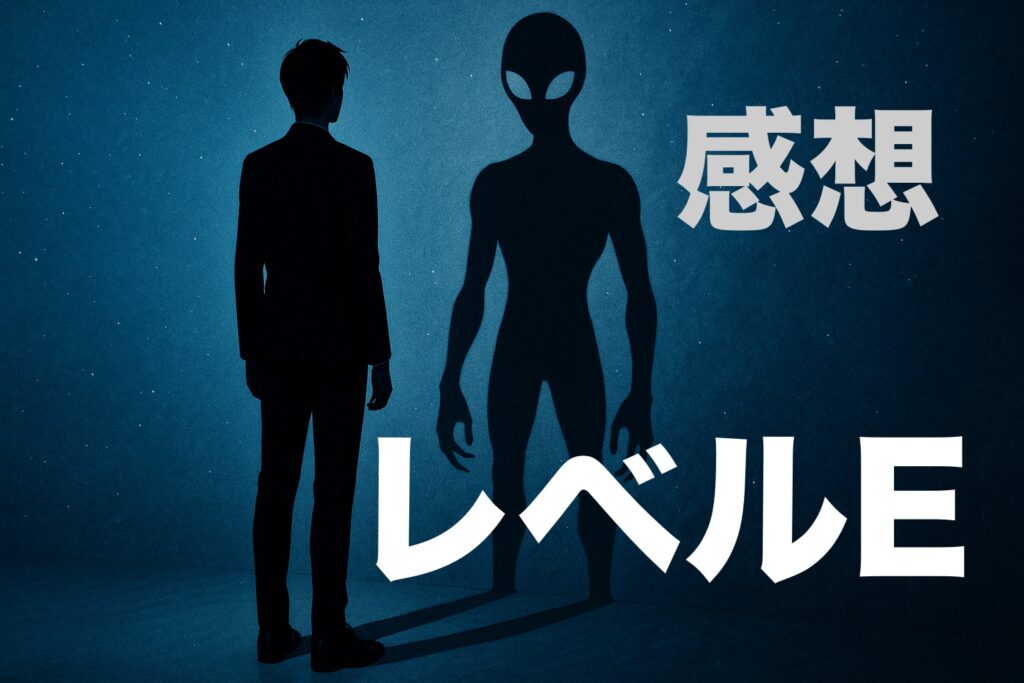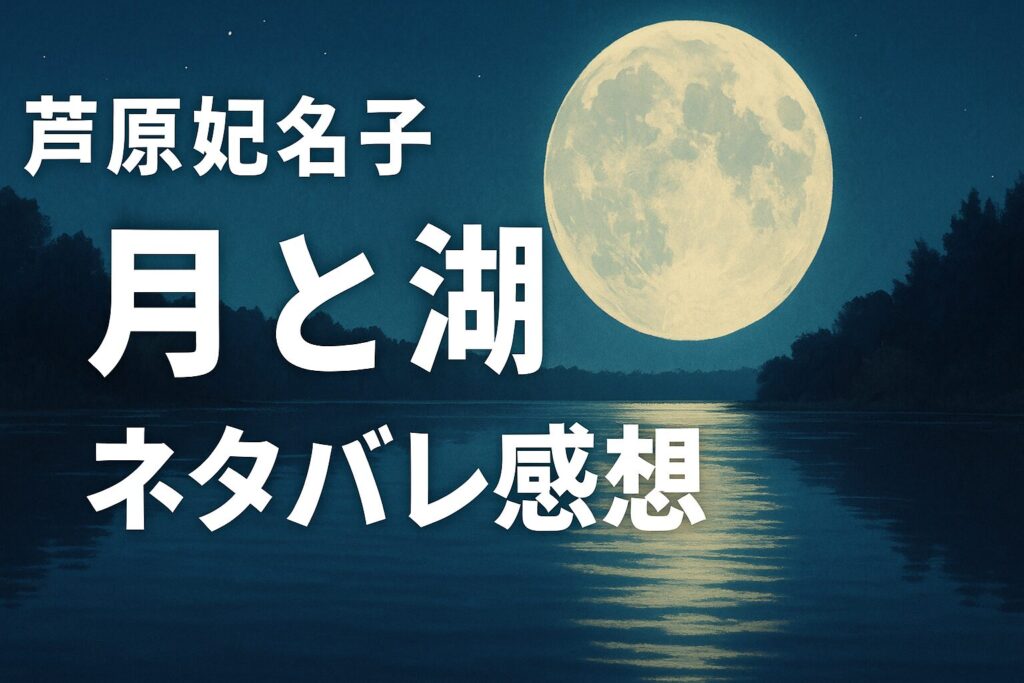今回は、中山七里さんのミステリー小説『犬を盗む』をご紹介!
今作は殺人事件の現場から一匹のチワワがいなくなったことをきっかけに物語が展開していく。
刑事たちの地道な捜査、犬を飼う人々の生活、ぽつぽつと登場する別々の視点。
それぞれが少しずつつながり、一つの事件の輪郭が浮かび上がっていく。
奇抜な設定やトリックで驚かせるタイプではないけれど、手がかりの拾い方が丁寧で、読むうちに静かに引き込まれていく。
物語は、日常に見えるものの中に潜む、わずかなズレを頼りに進んでいく。
今回はネタバレを避けて、そんな本作の導入部分を紹介していこうと思う。
今回ご紹介する作品はこちら!
中山七里『犬を盗む』あらすじ・ネタバレなし紹介|犬が消えた家から始まる静かな群像ミステリー
老女が一人暮らししていた家で、ある日遺体が発見される。
亡くなっていたのは木戸タカ子。
気難しい性格で、近所付き合いもほとんどなかったという。
捜査に当たるのは、犬が苦手な刑事・植村とその後輩・下山。
現場には湯呑みが二つ、部屋は荒らされ、金銭目的の犯行が疑われる。
だが何より引っかかったのは、犬の存在だった。
タカ子は犬を飼っていたはずなのに、その姿がどこにも見当たらない。
やがて、警察はタカ子の娘・仲野美智を呼び出す。
だが親子関係は冷え切っており、ほとんど連絡も取っていなかったという。
弟が二人いるが、一人はアメリカ在住、もう一人は札幌で会社を経営しているらしい。
家族の中に事件の手がかりはなさそうに見えた。
一方、物語は別の場所にも視点を移していく。
コンビニで働く若者・鶴崎は、一匹のチワワを飼い始めたばかりの同僚・松本の家を訪ねる。
出版社で働く小野寺真希は、夫や飼い犬とともにドッグランへ通う日々に、少し倦み始めている。
そのドッグランには、複数の飼い主たちが出入りしていた。
登場人物たちは、それぞれの日常を過ごしているように見える。
だがその背景には、小さなすれ違いや、うまく言葉にできない不満が潜んでいる。
そして彼らが持つ「犬との関係」は、思いがけないかたちで事件と重なっていく。
中山七里『犬を盗む』感想と見どころ|日常のズレが繋がる群像劇型ミステリー
この作品の面白さは、いくつもの視点が静かに並行して動き始めるところにある。
最初は一軒家で起きた変死事件から始まるけれど、そこに直接関係のなさそうな人々のパートが挟まれていく。
――コンビニ店員の会話。
――ドッグランに集う飼い主たちの何気ないやり取り。
――そして、時々差し込まれる、“とある犬”の視点。
それぞれのエピソードが独立しているように見えて、読み進めるうちに少しずつ、ひとつの点に向かって重なりはじめる。
この人たちは、どこでどう繋がっているのか?という疑問が、だんだんと読者の中に積もっていく。
登場人物たちは皆どこか静かで、淡々と日常を過ごしているように見える。
でも、その中には小さな違和感や、言葉にならないまま放置された嘘が潜んでいる。
そして、時折登場する“犬の目線”は、人間たちの表情や空気を、まったく違う角度から映し出す鏡のように働いている。
派手なトリックやテンポのいい展開よりも、「静かなズレや、関係のほころびを拾っていくタイプのミステリー」が好きな人に向いている一冊。
本当に「盗まれた」のは何だったのか?
タイトルの意味も、物語が進むにつれて少しずつ見えてくる。
中山七里『犬を盗む』はこんな人におすすめ|犬が好きな人もミステリー好きもハマる一冊
 焦げ団子
焦げ団子今作はこんな人におすすめだぞ!
犬が好きな人も、ちょっと苦手に思ってる人も、共感できる描写がある
この作品には、ただ犬を愛でる人だけでなく、犬との距離感に悩んだり、割り切って接している人たちも登場する。
たとえば、犬好きな人は当然として、「犬は飼っているけど、ドッグランの独特な空気がどうにも苦手」というキャラもいれば、そもそも犬が嫌いな刑事までいる。
それぞれが犬とどう付き合っているかを通して、人との関係性やその人自身の性格までもが段々と浮き彫りになってくる。
犬に対して何らかの感情を持っている人なら、どの立場から読んでも、なにかしら引っかかる場面があるはずだ。
群像劇が好きな人にも刺さる構成
視点はひとつに固定されず、まったく接点のなさそうな人物たちが次々と登場する。
コンビニで働く若者、出版社勤めの女性、ドッグランに集う飼い主たち。
それぞれのエピソードが単独で進んでいくように見えて、
ある一点に向かって、少しずつ線が交差していく構成になっている。
「この人たち、どこで事件に関わってくるんだろう?」という疑問を持ったまま読み進めることで、視点が切り替わるたびに小さな伏線が積み上がっていくのが気持ちいい。
ラストに向けて、それらがどう繋がっていくかを楽しむのもこの作品の醍醐味だ。
派手さよりも、静かなミステリーが好みの人へ
この作品には、大がかりなトリックやどんでん返しといった派手な仕掛けはない。
かわりに描かれていくのは、会話の中のちょっとしたズレや、登場人物同士の距離感・違和感。
「え、それさっきと言ってること違わない?」
「この人、なんでそこでそんな反応するんだろう?」
――そんなふとした場面が、読み進めるうちに静かに引っかかってくると思うので、その引っかかりを覚えておくと、後になって「あれってそういうことか」とつながる瞬間が訪れる。
全体像が一気に明かされるような派手さはないけれど、会話の端々や、些細な仕草の違和感が、少しずつ手がかりとして積み上がっていく。
その流れを追うのが、この作品の静かな面白さになっている。
中山七里まとめ|『犬を盗む』は“静かに違和感が滲む”タイプの良作ミステリー
筆者は普段は刺激的な作品を好むけれど、この作品は静かに進むぶん、登場人物たちの空気の揺らぎがかえって際立っていて、気づけば最後までしっかり読んでいた。
また、うちの実家でも犬を飼っているけれど、だからこそ犬の仕草や犬をとりまく人間関係の描写もあるあるだなあと共感するところが多かった。



登場人物の「犬との向き合い方」がバラバラなのが、この物語の面白さでもある。
派手な展開はないけれど、日常の中の小さな違和感からじっくり真相に近づいていくミステリー。
犬が好きな人にも、ミステリーが好きな人にも、ちゃんと届く一冊です。
書評カテゴリの最新記事
今回ご紹介した作品はこちら!