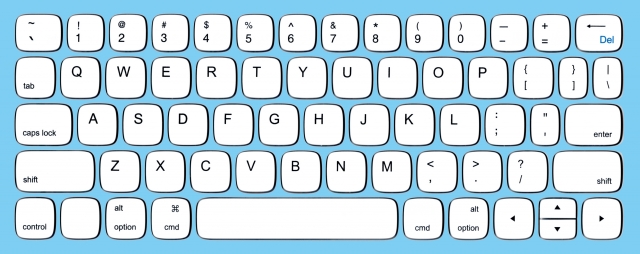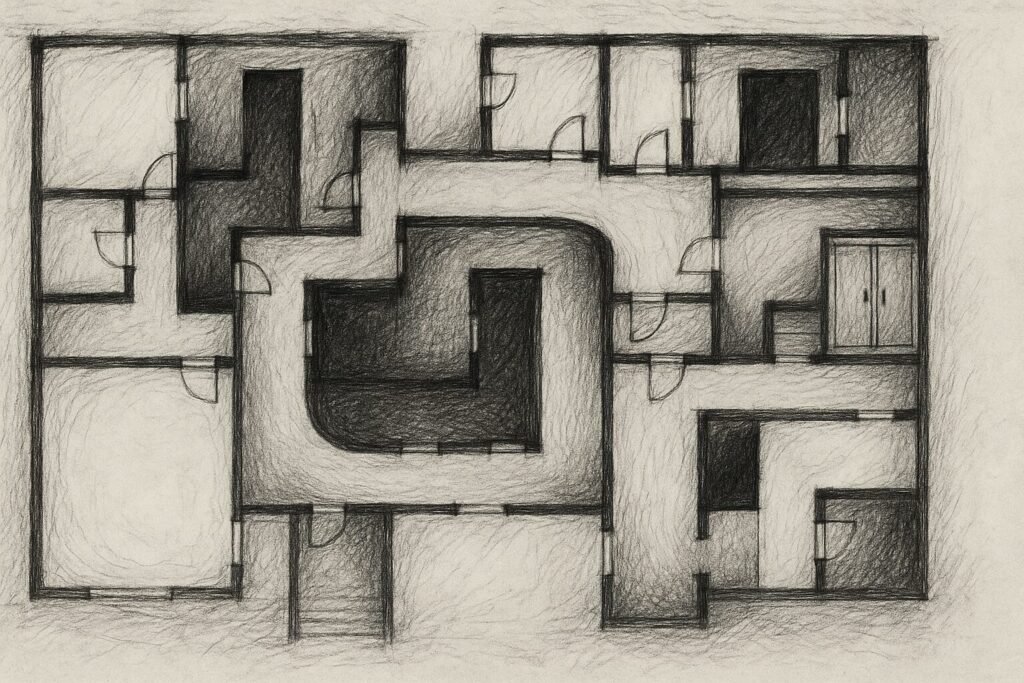焦げ団子
焦げ団子なんでキーボードって、ABC順じゃないんだ?
最初にPC触ったとき、団子は本気で思った。
だって「A」は左上にあるのに、「B」や「C」は全然違う位置。
QWERTY(クワーティ)って…誰だよお前。
……と、ここで軽く説明しておこう。
QWERTY(クワーティ)配列とは、
キーボードのいちばん左上にある 「Q・W・E・R・T・Y」 という並びの頭文字をとってつけられた名前。
つまり、別に「クワーティさん」が発明したわけではない。
安心してくれ。そういう海外の学者とかじゃない。
とはいえ、なんでこの謎配列が主流になったのか?
その理由には、タイピスト時代の裏事情があったりする。
今回は、そんな謎のキーボード配列のルーツを真面目に、でも団子的にザックリ解説していく!
- QWERTYって誰が作ったの?
- そもそもなんでABC順じゃダメだったの?
- 他にも配列あるの?
そのへんの謎を、今こそタイピングの深淵からあばいてやろうではないか!!
【関連記事】タイピストの歴史についてもまとめてます
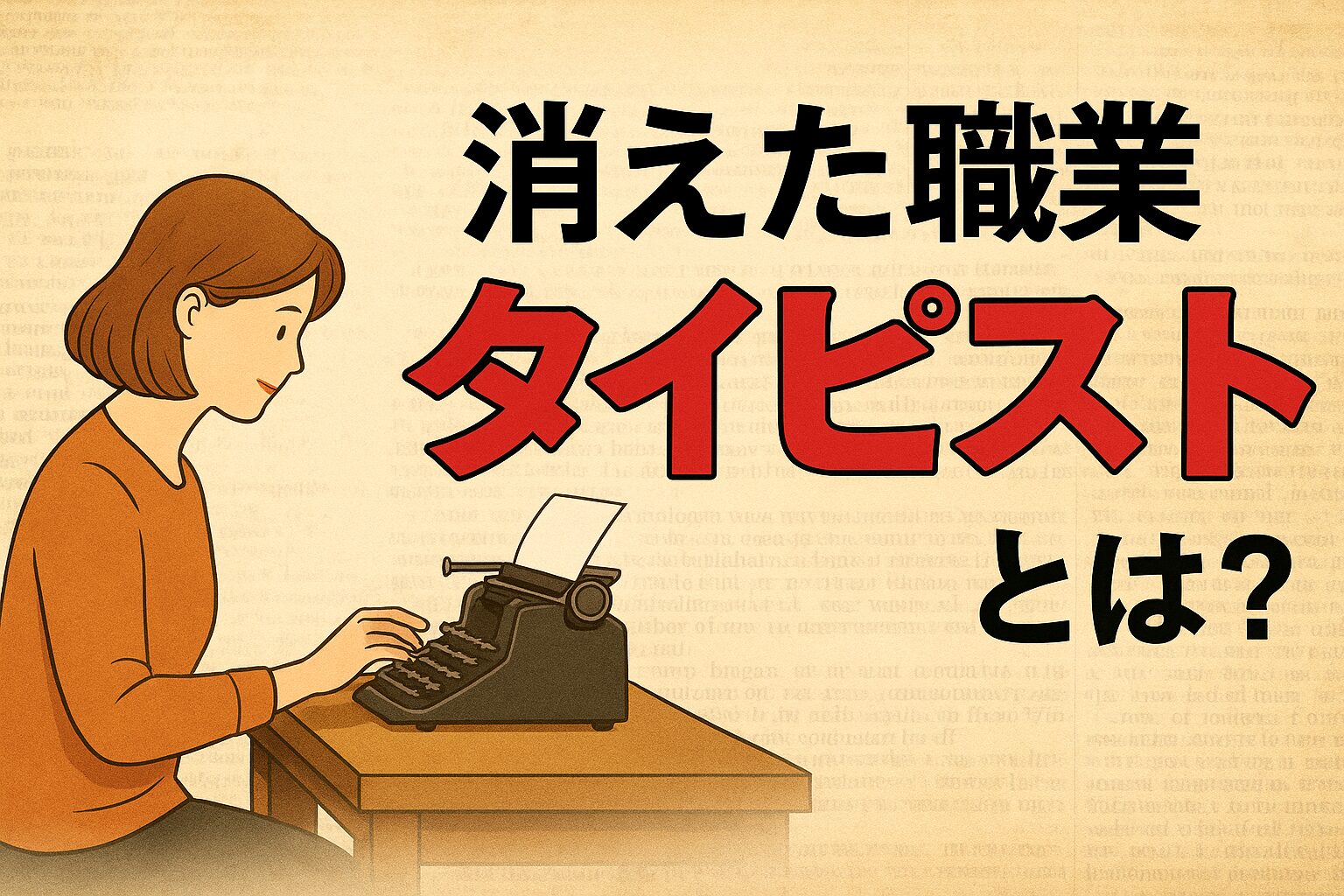
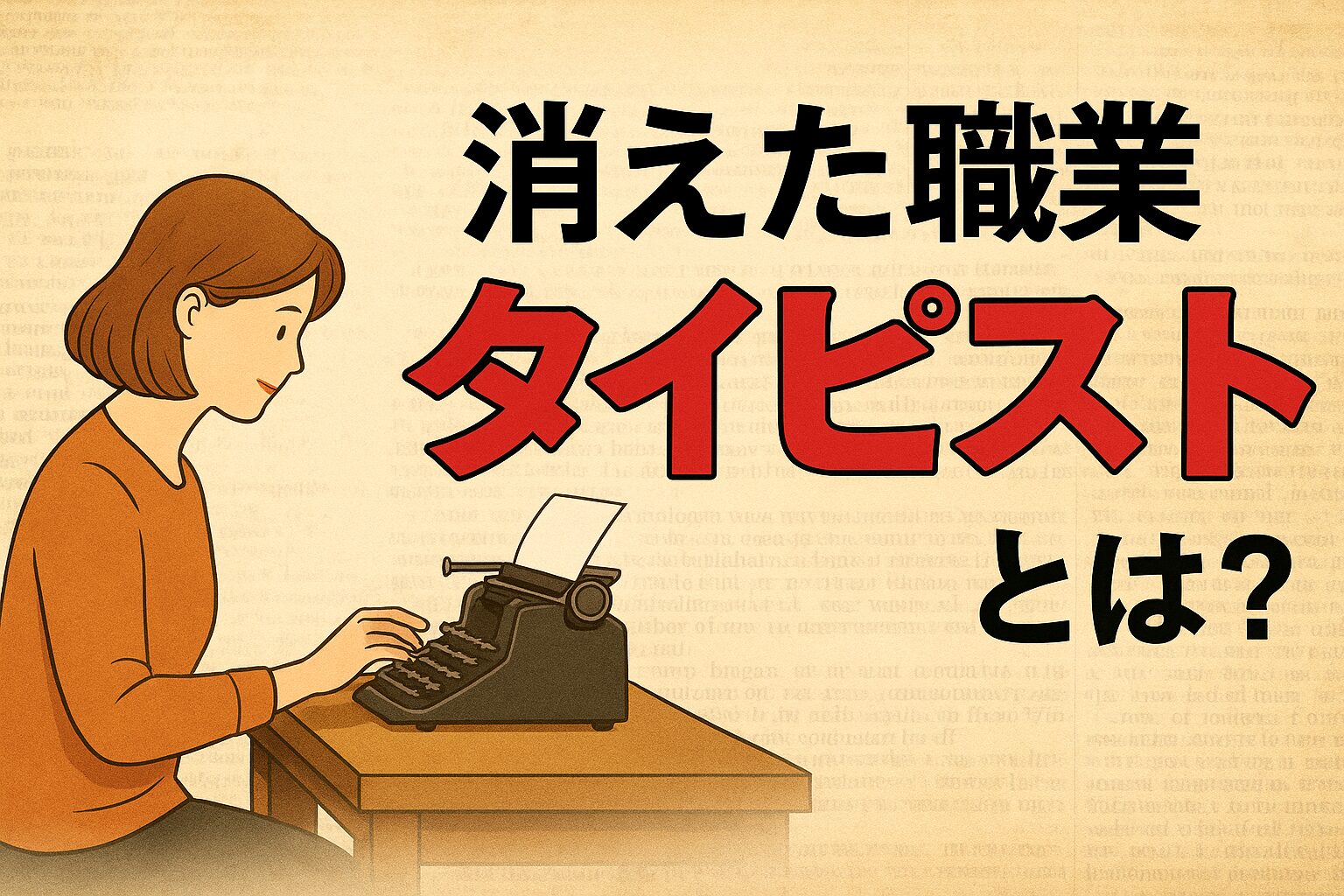
団子おすすめのロジクールのキーボードはこちら
なぜABC順じゃない?キーボード配列の謎の起源


A・B・Cの順に並んでたら、どれだけラクだったか…
誰しも一度は思ったことがあるこの疑問。
でも実は、あの謎の配列「QWERTY」には、ちゃんと理由があった。
QWERTY配列が生まれたのは、1870年代のアメリカ。
発明したのは、クリストファー・レイサム・ショールズというおじさん。
この人、世界で初めて市販されたタイプライターを開発した人物なんだが、当初のキーボードは当然、ABC順だった。
しかし、タイプが速すぎてキーが絡まるという大問題が発生。
ガチャガチャと文字を打つたびに、内部の金属アームがぶつかって詰まる。
このままじゃ実用にならん!ということで、「よく使う文字の組み合わせを、あえて離れた位置に配置してタイピングを遅くさせる」というトンチキみたいな設計が登場する。
これが後にQWERTY配列として定着していくのである。



進化の始まりがタイピングを遅くするためってどういうことだよ!!
なぜQWERTY配列が勝ってしまったのか?
QWERTY配列って、実はそんなに効率のいい配列じゃない。
もともとはタイプライターで「キーが引っかからないように」っていう理由で設計されたものだから、人間が打ちやすいようにとか、疲れにくさを考慮して作られたわけじゃない。
その後、「いやもっと打ちやすくした方がよくね?」ということで登場したのがドヴォラック配列だ。
この配列、母音を全部左手のホームポジションに集めて、右手にはよく使う子音を配置。打つときに指があっちこっちに飛び回らなくても済むよう、すごく考えられてる。
しかも両手のバランスも良くて、左右交互にタイピングできるよう設計されてるから、リズムも自然でスピードも出やすい。
なのに、まったく普及しなかった。
理由はシンプルすぎて悲しいけど、「もうQWERTYが広まりすぎてたから」。
タイピストの学校も、企業の書類も、新聞社の編集部も、ぜーんぶQWERTY前提で動いてた。
そこにドヴォラック配列持ち込んでも、「今さらそれ覚えるの!?」ってなる。教育コスト、印刷コスト、機材の入れ替え――どれを取っても非現実的だった。
つまり結局、「合理的かどうか」じゃなくて、「みんながもう使ってるかどうか」で勝敗が決まった。



最適解じゃなくて、既に広まってる方が勝つのインターネットの謎ルールみたいで好き。
ドヴォラック配列は今も使えるの?
実はドヴォラック配列、今でもちゃんと使える。
WindowsにもMacにも、地味に標準で入ってる。設定画面から変更すれば、QWERTY配列のキーボードでも、ドヴォラック配列で入力できるようになる。
じゃあ使ってる人いるの?って話になるけど——少数派すぎる。
「タイピングをゼロから学び直してでも効率を追い求めたい」みたいなガチ勢の中には、ドヴォラック派もいるっちゃいる。
でも多くの人にとっては、QWERTY配列のままで困ってないし、学習コストもでかすぎる。
なんなら「US配列すら使いづらい」って人も多いのに、ここにさらにドヴォラック持ってくるって、まあハードルが高いよね。
だから結局、選ばれたのはQWERTY。
効率性よりも慣れが最強ってことを証明してしまったわけである。



ベストな選択肢より、みんなが使ってる選択肢のほうが生き残る。
もう、人生ってだいたいそういうもんだよな(遠い目)。
まとめ:最適じゃなくても当たり前になったもん勝ち
キーボードがABC順じゃない理由、それは「打ちやすさ」でも「科学的な理由」でもなく、歴史と習慣の積み重ねだった。
- 打ちづらいのは、むしろ“故意”だった(初期の機械のため)
- ・効率を追求した配列はあった(ドヴォラックなど)
- ・でも、一度広まったQWERTYに誰も勝てなかった
今もなお、私たちは「最初に決まったルール」に従ってタイピングしてる。
便利さよりも、みんなが使ってるからという理由で。
団子的に言うと、「非効率なスタートでも、標準になったら勝ち」ってのは、キーボードに限らずけっこう人生にもあるよな…。
というわけで、今回はちょっとしたタイピングの裏話でした!



また面白い雑学を見つけたら記事にするぞー!
【関連記事】タイピストの歴史についてもまとめてます
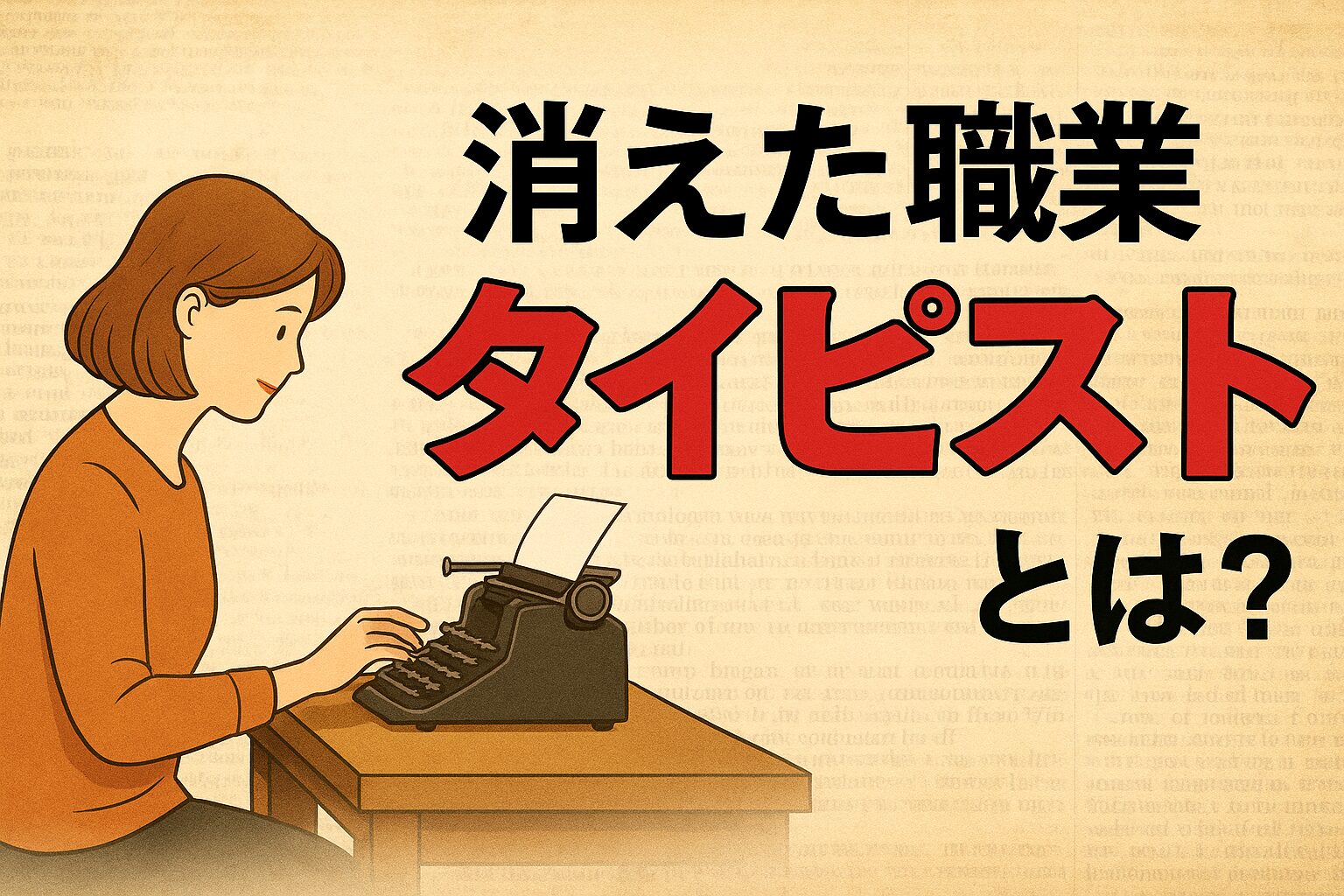
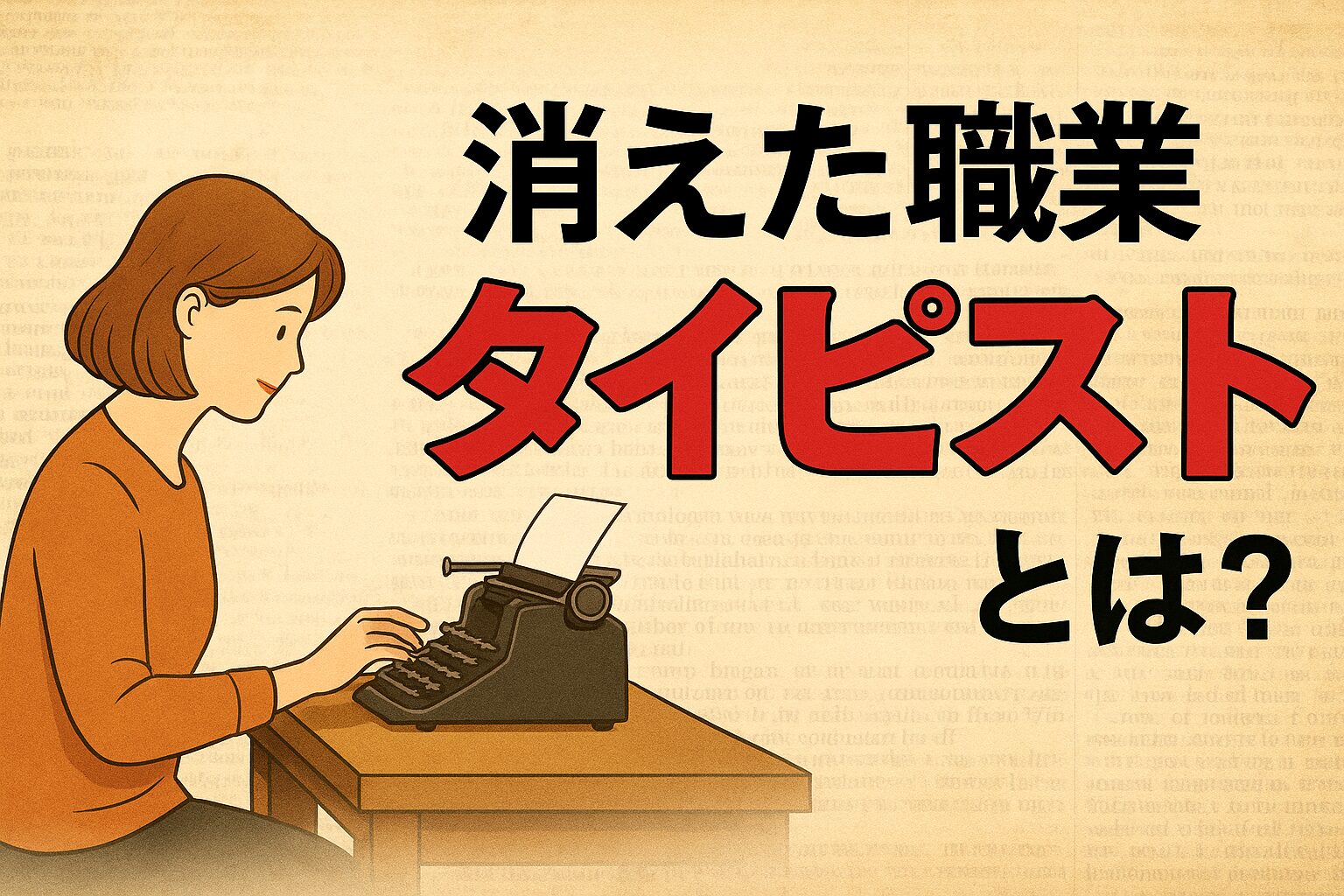
QWERTY配列の歴史を知ったら、タイピング環境も見直したくなるはず。
【疲れにくい/静音/打鍵感が気持ちいい】おすすめキーボード、団子的にセレクトしました▼
Webカテゴリの最新記事