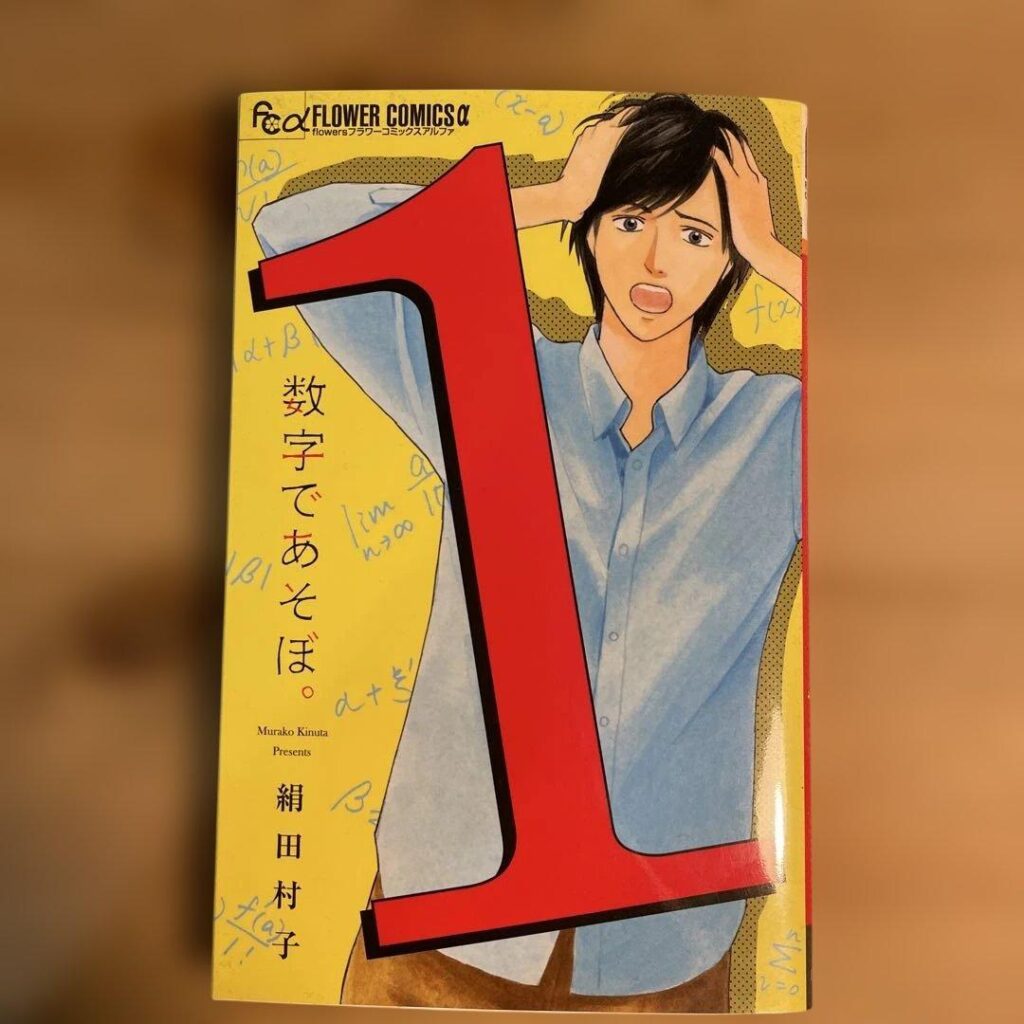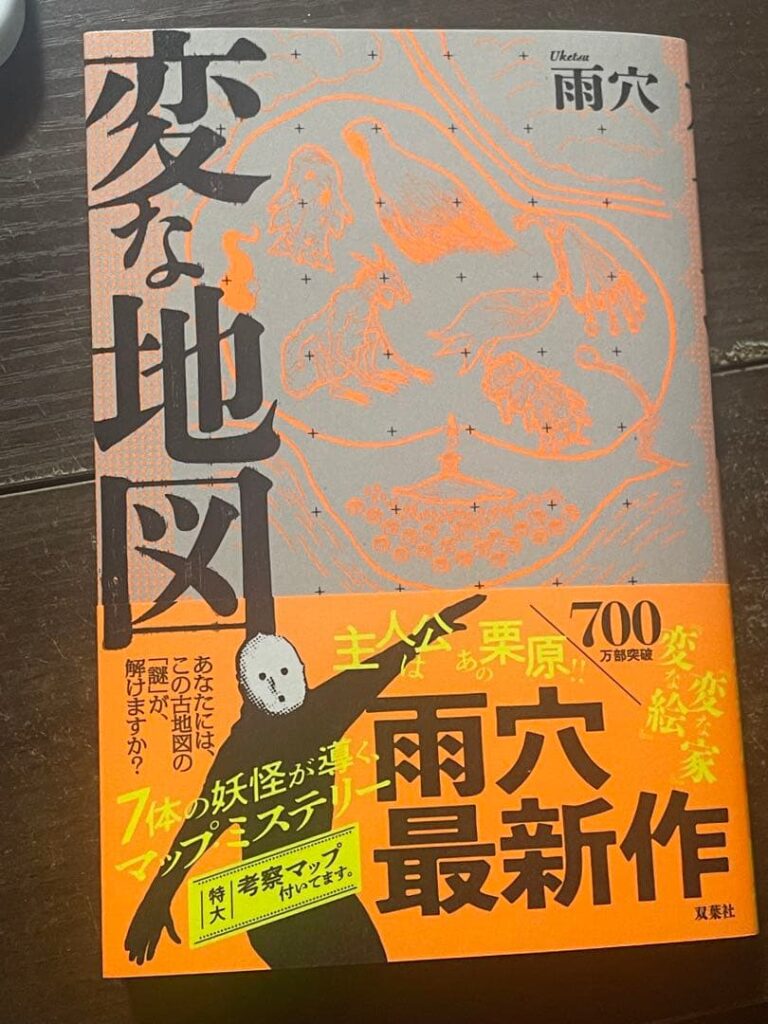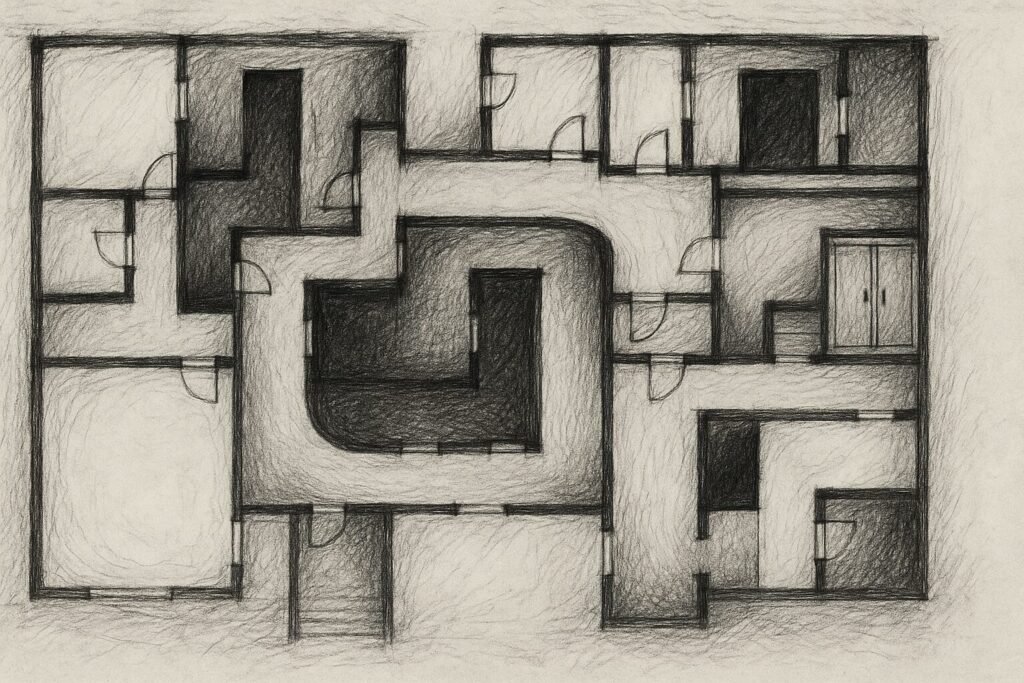少し前にお亡くなりになった漫画家芦原妃名子さん
実は結構前から団子はこの漫画家のファンだった。
中でも芦原妃名子さんの短編『月と湖』。この話がとても好きだった。
一言でまとめれば、「祖父の愛人と暮らすことになった女子高生の話」。
でも、そんな単純な一言では片付けられない“揺れ”が、そこにはあった。
愛された祖母と、愛した側の愛人。
裏切られたと思っていた少女が、たった10日間の生活で目にしたものとは何だったのか。
“浮気”や“不倫”といったワードではとても語れない、もっと複雑で静かで、でも確かに心に刺さる何かが描かれていた。
今回は、この作品を読んで感じたことを、できるだけ丁寧に言葉にしてみたいと思う。
芦原妃名子『月と湖』ネタバレあらすじ|祖父の“裏切り”から始まる、静かな再構築の物語

市原一菜(いちはら かずな)は、小説家である祖父・市原有生の死をきっかけに、彼の知られざる過去と向き合うことになる。
祖父は「月と湖」というタイトルの私小説を遺していた。その内容は、自身の妻(=一菜の祖母)ではない女性との恋愛を赤裸々に綴ったものだった。
世間からは“純愛小説”と絶賛されたが、一菜にとっては祖父の裏切りを突きつけられたような衝撃だった。
そんなある日、祖母の絹子から「その小説に登場する“元愛人”が病気で倒れたらしい」と告げられる。
「よかったら様子を見に行ってあげてくれない?」と頼まれた一菜は、内心複雑な思いを抱えながらも、祖父の“相手”に会うことを決意する。
訪れたのは、自然に囲まれた山間の静かな家。そこで出会ったのは、快活な老女・水原透子だった。
彼女は、祖父の別荘の近くで無農薬野菜を育てながら静かに暮らしている人物だった。派手さや妖艶さは一切なく、親しみやすく、でも凛とした人。“愛人”というイメージとはまったく違っていた。
最初は警戒し、戸惑っていた一菜も、透子との静かな共同生活の中で、少しずつ心を開いていく。食卓を囲み、野菜を育て、ぽつりぽつりと過去を語り合う10日間。
その中で一菜は、祖父が妻以外の女性を「本気で」愛していたことを実感し、同時に、自分の恋愛にも重なる感情を覚えていく。
というのも、一菜は大学生の彼氏・松下航太との関係に悩んでいた。高校時代からの付き合いだったが、大学に進学した航太の気持ちがだんだんと離れていくのを感じていた。
そんなある日、透子の口から祖父との思い出が語られる。
それは、「奪う恋」でも「壊す恋」でもなかった。
「愛されていた」ことより、「愛したかった」ことの方が、透子にとっては大切だった――
そんな想いを知った一菜は、祖父を責める気持ちから解放されていく。
そして春休みの終わり、一菜は透子に別れを告げ、自分自身の気持ちに決着をつけるために、もう一度、航太と向き合う決意をする。
芦原妃名子『月と湖』感想・見どころ

愛された記憶と、冷めていく現在とのギャップ
この作品では、一菜と航太の“馴れ初め”がかなり丁寧に描かれている。同じサークル、好きな作家の話題で盛り上がり、自然と惹かれ合っていったふたり。
まさに「始まりのきらめき」が詰まったような関係だ。
だけど、大学に入って少しずつ変わっていく距離感。頻度が減る連絡、曖昧なままの会話、心に刺さる違和感。最初の“きらきらした思い出”がある分だけ、冷めていく今がリアルに突き刺さる。
しかも、どちらも中途半端に優しいから、決定打もないし終わらせられない。
 焦げ団子
焦げ団子この「言い出せなさ」と「でももう分かってる感」
――たぶん誰しも心当たりがあるんじゃないか。
「奪う女」って本当に“悪”なのか?
浮気相手というと、わかりやすく“色気ムンムン”で“悪女”っぽい女性が出てくることが多い。けど、『月と湖』ではそのテンプレを徹底的に壊してくる。
航太の“多分浮気相手”である芙美は、後輩思いでやわらかい、誰にでも優しくできる子として描かれている。
祖父の元愛人である透子も、健康的でサバサバしていて、決して“男を誘惑して奪う”ようなタイプではない。むしろ、二人とも本当にいい人だ。
だからこそ、読んでいて混乱する。



“奪う側の女”が悪人じゃないとしたら、何を責めればいいのか?
「誰でもそうなり得る」ものなのか?
それとも、誰かを好きになるって、そんなに単純に割り切れるものじゃないのか?
「手に入れた」と思った瞬間に、関係は壊れ始める
一菜は透子に言う。「あなたたちが羨ましい。だって愛されてたんでしょう?」
でも透子は、あっさりと返す。
「私も彼を手に入れたなんて、思ったこと一度もなかった」
この言葉にすべてが詰まってる。
どんなに“愛された”と思っていても、人は誰かを完全に手に入れることなんてできない。それでも、人は誰かを愛し、愛されたことを信じたがる。
一菜がそのあと、本妻である祖母に同じような問いをぶつけるシーンが強烈だ。
「あんな小説まで残されて、それでも一緒にいられてよかったと思う?」
でも、祖母は少し笑って答える。
「男の人って、愛してるって言いながら女に恋してるふりして、本当はもっと遠くを見てるのよ。
夢とか野望とか、ロマンとか。
女はね、そんな殿方が、愛しくてたまらないの」
この台詞、あまりにも…あまりにも深い。
“選ばれる側”から、“選ぶ側”へ
作品の最後、一菜は静かに航太に別れを告げに行く。何かをぶつけるわけでもない。問い詰めるわけでも、責めるわけでもない。
ただ、自分で気づいたのだ。自分は祖母のようにはなりたくない。
「選ばれるのを待つ恋は、もうやめよう」と。
選ばれなかったから魅力がないわけじゃない。ただ、相性とか縁とか、タイミングが合わなかっただけ。
一菜が踏み出したのは、誰かに選ばれる恋じゃなく、自分で選び、自分で決めていく恋だった。
芦原妃名子『月と湖』感想|「愛されなかった」じゃなくて「選ばれなかった」だけかもしれない
浮気や不倫をテーマにした話って、どうしても「悪者」と「被害者」がハッキリ描かれることが多い。
でもこの作品は、そういう単純な構図にせず、誰もが“誰かにとっての愛の対象になりうる”ことと、同時に“ならないこともある”という現実を描いていたように思う。
祖父の元愛人・水原さんも、彼氏の周囲にいる女性も、誰も「奪う側」「奪われる側」にきっちり収まってはいない。
それぞれが迷って、揺れて、それでも関係を選ばざるを得なかっただけ。
そして一菜もまた、自分が「選ばれなくなっていく」側の気配に気づいていた。
でも、そこで「誰かに選ばれること」じゃなくて、「自分で自分の立場を選ぶこと」を選んだ。
その変化が、すごく印象的だった。
「選ばれなかったから価値がないわけじゃない」
「たまたま縁や相性がすれ違っただけかもしれない」
そんなふうに思えた瞬間から、人って少しだけ前を向けるのかもしれない。



正解は誰にもわからないけど、“わかりたい”って思うことが大事
まとめ|芦原妃名子『月と湖』が照らす、愛と選択の物語
短編『月と湖』は、単なる浮気の話ではない。
愛された側、愛した側、そして傍でそれを見つめる第三者――どの立場にも、それぞれの言い分と矛盾、そして正しさと弱さが描かれている。
祖父の愛人だった女性が、魅力的で、明るく、まっすぐだったように、彼女を許した祖母にも、確かな愛情と寛容さがあった。
そして主人公の一菜が、「選ばれること」に振り回されず、「選ぶこと」を選択したように。
この物語は、“誰かを傷つけること”と、“誰かを大切に想うこと”が、時に同時に存在してしまう現実を、淡々と描き出していた。
どちらが正しいか、誰が悪いか。答えを出すのではなく、「人はこうして揺れる」ということを見せてくれる。そしてその揺れを知ったからこそ、一菜は少し大人になれた。
恋愛に限らず、「なぜ選ばれなかったのか」「本当に愛されていたのか」そんな問いにぶつかったとき、ふとこの作品を思い出してみてほしい。
きっと、「それでも大丈夫だ」と思えるヒントが、どこかにある。
そんなふうに考えると、今は芸能人の浮気だの不倫だので世間は騒ぎ立てるけど、本当はもっと、本人たちにしかわからない感情や背景があるんじゃないかとも思えてくる。
一言では言い切れない出来事や揺れに、ただ名前をつけて、線引きしてしまうのは、もったいないことなのかもしれない。
書評カテゴリの最新記事