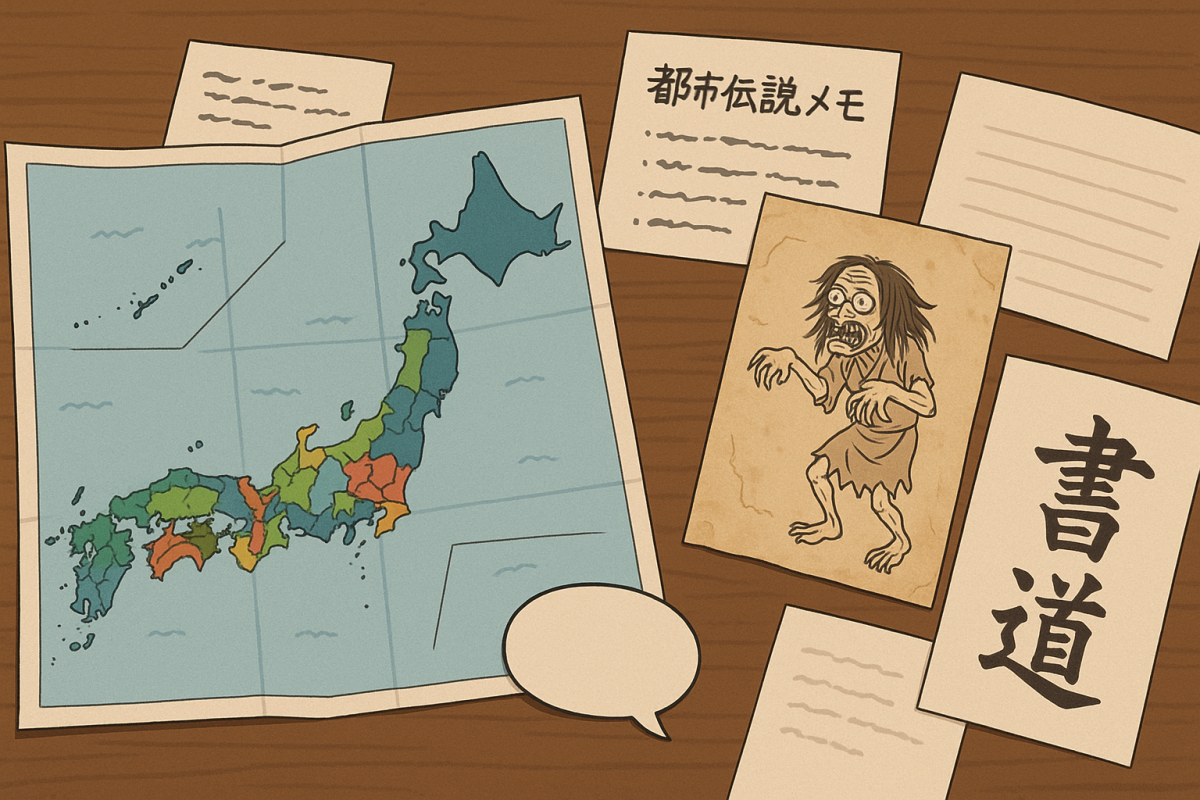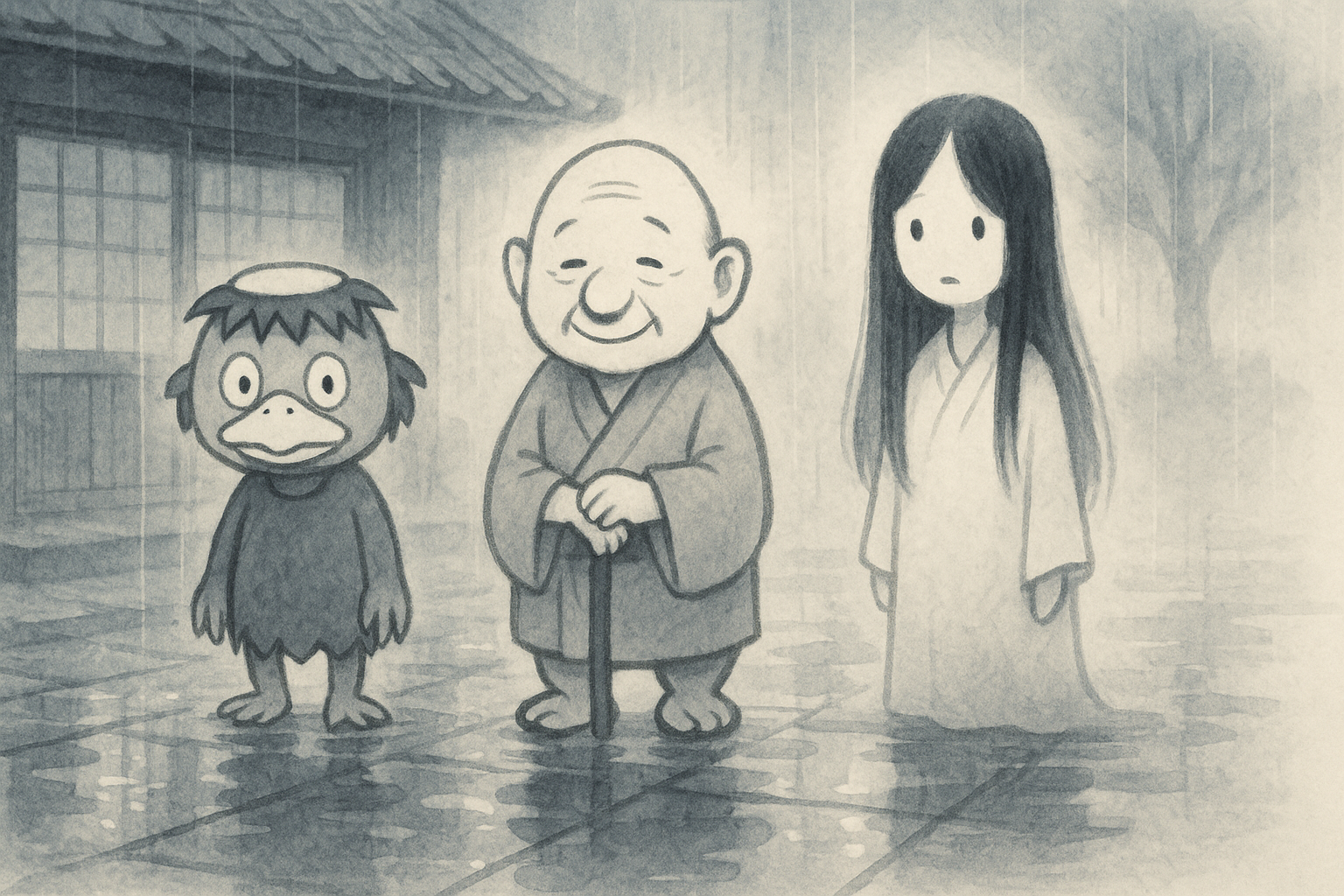昔の妖怪って、やたら濡れてない?
河童、海坊主、ぬらりひょん、雪女、あまびえ、傘おばけ……
思い返してみると、ジメジメ・ヌルヌル・しっとり系がやたら多い。
なんで? 湿度で発生でもしてんの?
それとも日本の妖怪、乾いてると力出ない縛りでもあるの?
そんな違和感から始まったこの記事。けど掘ってみたら、「水」と「情緒」と「人間の不安」のドロドロした関係性が見えてきた。
今回はそんな“濡れすぎ妖怪”たちの裏側を、団子的文化史視点でぬめっと深掘りしてみる。
歴史ってこんなにヘンテコで、こんなに面白かったっけ?
▼他にも“クセつよ文化史”ネタまとめてます。
文化史コラムまとめ一覧→焦げ団子がひもとく文化の断面図一覧
濡れてる妖怪、多すぎない?
昔話でも妖怪図鑑でも思い出してみてほしい。なんか…濡れてるやつ、多くない?
河童:言わずと知れた水棲界のトップスター。皿乾いたら即命の危機。
海坊主:もはや“海そのもの”。波と一体化して出てくるタイプ。
ぬらりひょん:名前の響きからしてヌメヌメ。正体不明の湿気感。
雪女・あまびえ:女系もだいたい水属性。
気づけば周囲はジメジメ系妖怪だらけ。もしかして日本の妖怪、
「乾いてると力出ない」って裏設定でもあるんか??
そんな疑問が湧いてくるくらい、濡れ系妖怪の占有率が異常に高い。
なぜ妖怪は水っぽいのか?背景を探る
なんでここまで“濡れた妖怪”ばっかり出てくるのか。それ、実は日本の風土と人間の想像力のクセが、がっつり関係してる。
まず大前提、日本って超・湿気大国。梅雨、台風、川の氾濫、土砂崩れ…
「水=命をくれるけど、命も奪う」存在ってのが、昔から生活のリアルに根付いてた。
民俗学者・柳田國男も、川や海は異界との境界って言ってて、水辺は「神の通り道であり、得体の知れないものが出る場所」って考えられてた。つまり「水のそばには、何かいる前提」だったわけ。
さらに、濡れるっていう状態には
- まとわりつく
- 肌を伝う
- 気づいたら染み込んでる
みたいな、「逃れられないジメジメ感」がある。これがまた、妖怪の執着体質とめちゃくちゃ相性いい。
文化心理の観点でも、“水”ってのは感情や無意識の象徴とされがちで、フロイトやユングも「夢に出てくる水=潜在意識」って言ってたりする。
で、実際に日本の昔話とか伝承では、見えない恐怖・説明のつかない出来事が“水に化けて”出てくることが多い。
- 足元すくわれた=沼の怪
- 夜に川から声がする=河童
- 船が転覆=海坊主
→ ぜんぶ「水のせいにしておけば納得できる」っていう文化的処理。
だから水っぽい妖怪ってのは、自然現象の擬人化じゃなくて、人間の感情と不安の代弁者なのかもしれない。
濡れてる=ジメっとまとわりついて、しつこくて、気づいたときには取り憑かれてる。
つまり「情緒が物理化してる存在」。
日本の湿度が高いの、天気のせいだけじゃない説わりとマジであるかもしれん。
水属性妖怪は“情緒の塊”説
ここまで見てきて思うんだけど…水っぽい妖怪って、もはや“情緒の塊”じゃね?
だって水って形がない。容器に合わせて姿を変えるし、流れるし、溜まるし、蒸発もする。感情と一緒。
表情は穏やかでも内側では激流みたいなやつ。
心理学的にも、水は「感情・無意識・記憶・女性性」の象徴とされがち。ユングなんかは「水=集合的無意識」って言ってたし、夢占いでも「心の深層が水になって現れる」ってのは割と定番。
→ 要するに、水っぽい存在=感情が染み出してきた結果って考えると、めちゃくちゃ納得いく。それに妖怪って、「情に縛られて現世に残ってる存在」なことが多い。
- 海坊主=溺死者の怨念の集合体説あり
- 化け猫=飼い主への執着で化ける定番枠
つまり、情緒=湿気=水。濡れた存在は、感情にズブズブに浸かってる存在。ちなみに折口信夫は、「幽霊や妖怪は“未練”のかたまり」って考えてた。
未練って、論理じゃなくて情。
だから、ジメっとしてる。
だから、濡れて出てくる。
なんならもう、水属性妖怪=「情緒漏れ起こしてる存在」とも言える。
ぬらりひょんという“湿度の化身”
さて、ここまで「濡れ妖怪」について語ってきたけど、ここからは語感的に”湿ってる”代表「ぬらりひょん」について語っていきたいと思う。
正直に言う。ぬらりひょんは、実際には濡れてない。
水の妖怪かと言われたら、まったくそんなことはなくて、あくまで語感がヌルヌルしてるだけ。でもそれが逆に厄介。
「ぬらり」=ぬめっとした動き、「ひょん」=思いがけない登場。
見た目じゃなくて、“存在感が湿ってる”タイプ。
ぬらりひょんは、昔の文献でもかなり正体不明で、「気づいたら家に入り込んでて、当然の顔して茶をすする」みたいなやつ。
追い出そうとしても、「あれ?あの人誰だっけ…」ってなる。
→ “権威の仮面をかぶった空気のような存在”。
…で、ここからが団子的ポイント。現代社会にもいない?ぬらりひょんっぽい人。
- どこにも所属してないのに、なぜか会議に来てる人
- 名刺の肩書きがめちゃくちゃ曖昧なのに、偉そうな態度の人
- 「あの人誰?」って思うけど、誰も問いただせないまま場が進行するやつ
つまりぬらりひょんって、濡れてはいないけど、湿った空気をまとってる代表格なんだよな。物理的には乾いてても、空気をにじませて場を支配するタイプ――そういう湿度型ボスキャラ。
妖怪って本来、「人が名前を与えることで形になる存在」だけどぬらりひょんはむしろ、
“名前があっても形がつかめない”っていう最恐スペック。
団子的にはこう締めたい:
見えない、濡れてない、でも妙に気になる。
そういう“存在の湿気”って、実は一番怖いのかもな。
※ぬらりひょん自身が“水の妖怪”というわけではない。
ただしその語感・性質・立ち位置が、水のように形を持たず、つかみどころがなくて、入り込まれると厄介な存在に近い。
団子的には、物理的には乾いてるけど、存在感は湿ってる系の筆頭。
団子的まとめ|日本のジメジメ体質が生んだ怪物
ここまで書いといてなんだけど…日本の妖怪、マジで湿りすぎじゃね?
でもその“濡れっぷり”って、単なる見た目の問題じゃなくて、人間の感情とか、不安とか、言葉にできないジメジメが染み出した結果だったのかもなって思った。
特に、
- 泣きたいけど泣けないとき
- 怖いけど理由がわからないとき
- 忘れたいのに、頭にしつこくまとわりついて忘れられないとき
そういうときって
頭よりも、空気とか湿度の方が本音を教えてくれる。
妖怪ってたぶん、そういう“空気の不調”を代わりに形にしてくれてたんだよな。水ってさ、飲み物にもなるし死因にもなるし透明なはずなのに、いちばん底が見えない。つまり、いちばん人間に似てる。
妖怪が濡れてるの、しょうがないわ。人間がドロドロしてんだから。
乾いて見える人ほど中身はヌルヌルとしてるもんだよ。たぶんね。
歴史ってこんなにヘンテコで、こんなに面白かったっけ?
▼他にも“クセつよ文化史”ネタまとめてます。